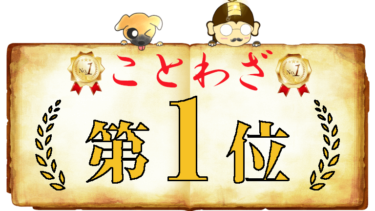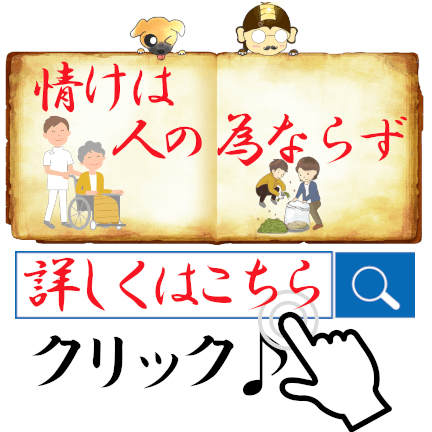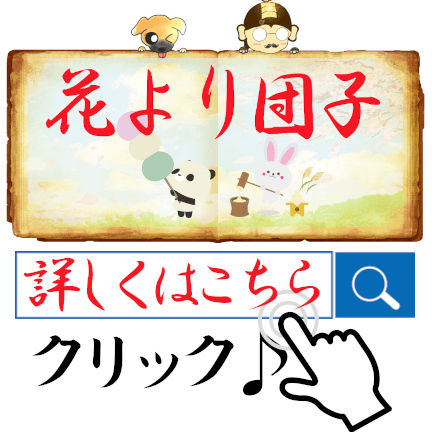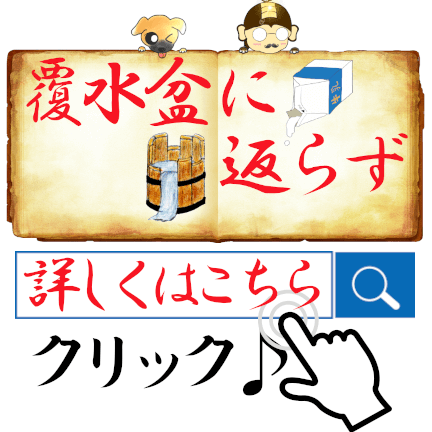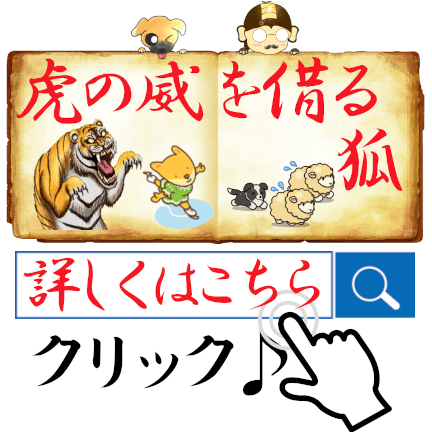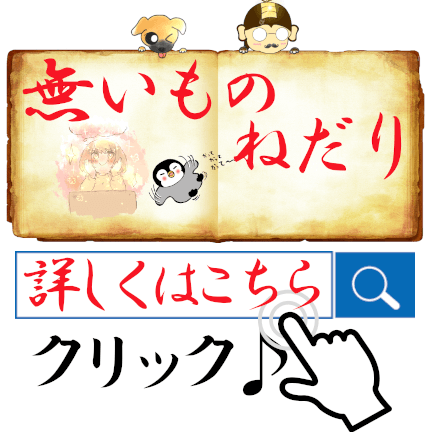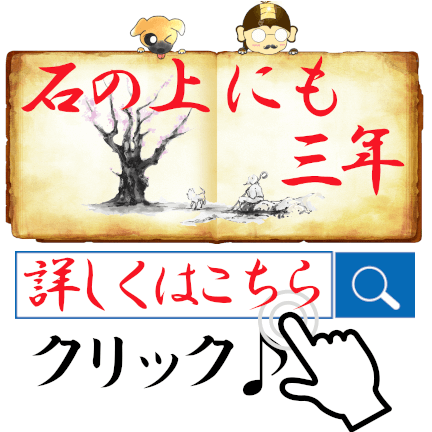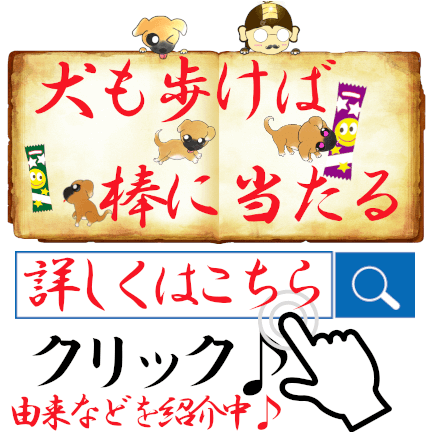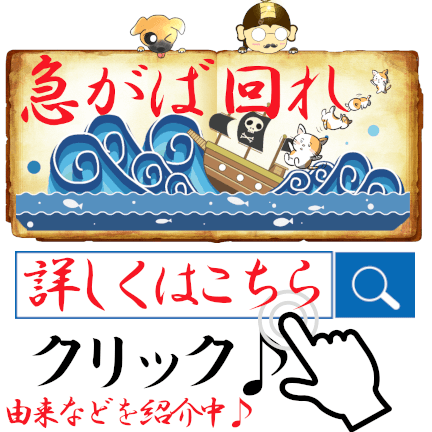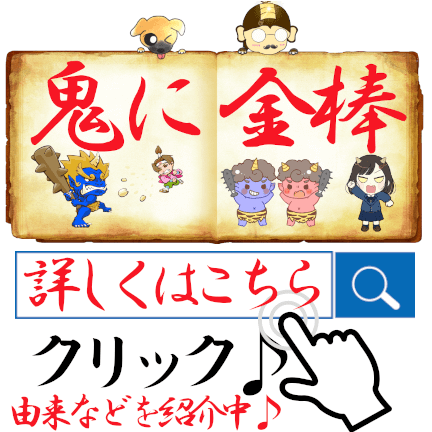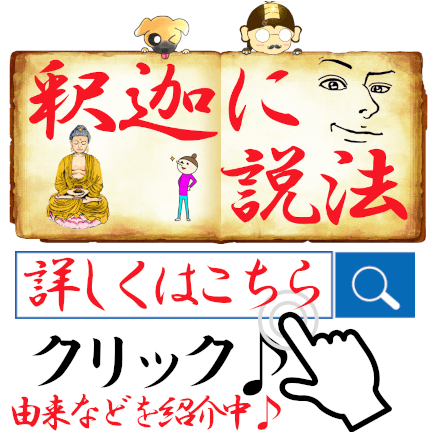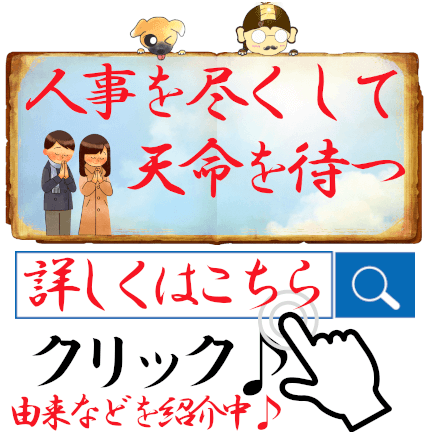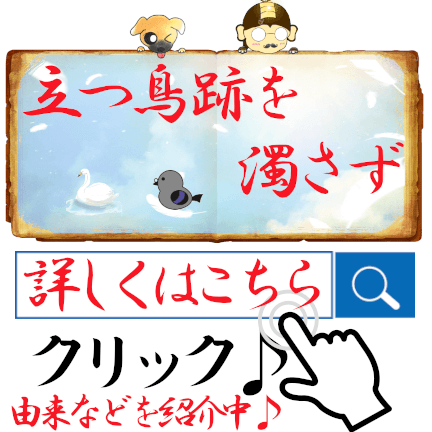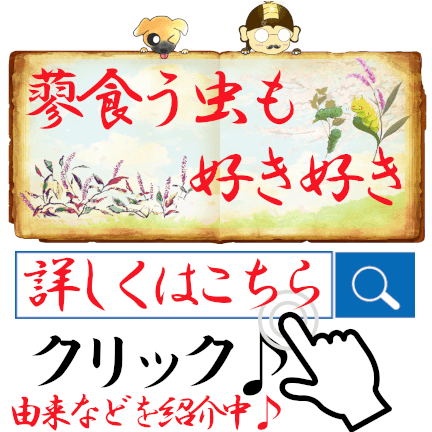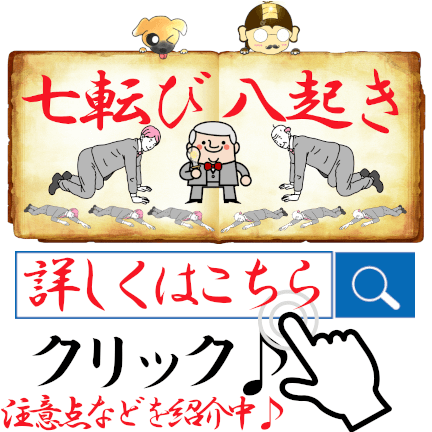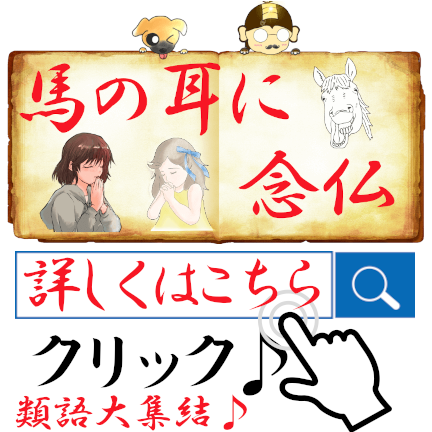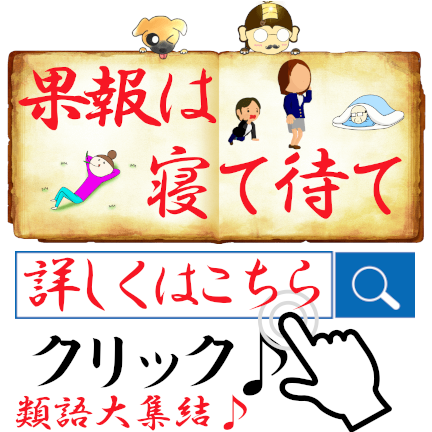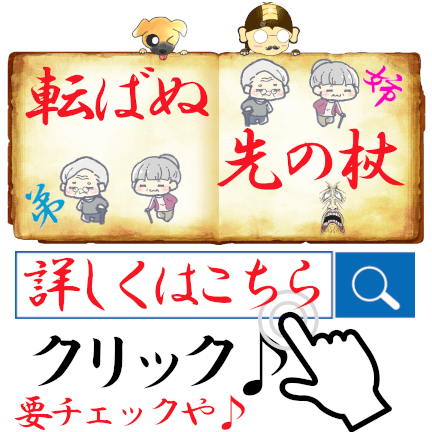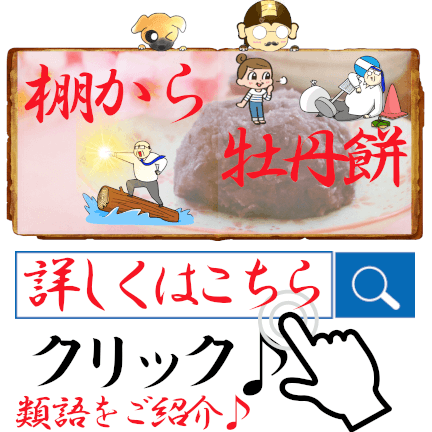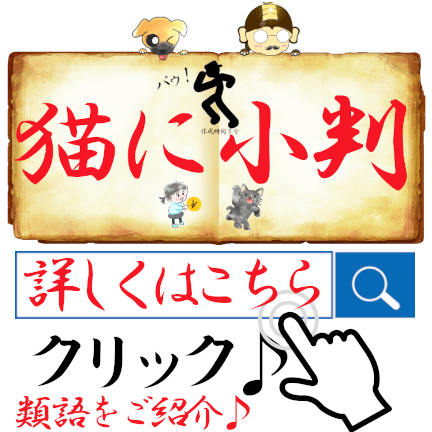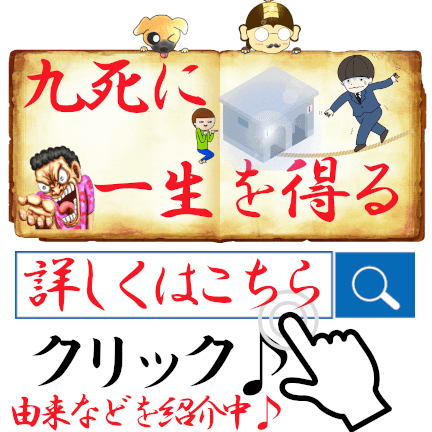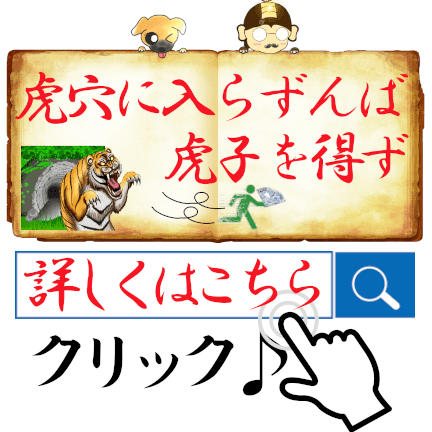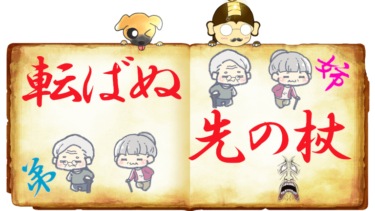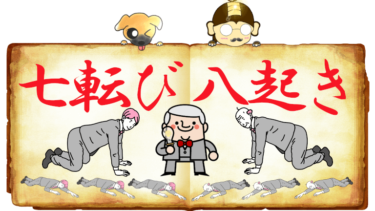漫画、小説、ドラマや映画。
好きなキャラや俳優が何気なく使っている台詞の中に、時折混じっている『ことわざ』
過去の人々により言い伝えられてきた知恵や教訓として、我々の日常にもさりげなく聞こえてきたりもします。
みなさんは最近、どんなことわざを使いましたか?
このページでは、1番知りたい!と思われていることわざをご紹介すると共に、No1にならなくてもいい検索数の多いモノから少なくても知っているような、元々有名なことわざもご紹介!
言葉によっては意味や由来なども記載していますので、生活のふとした知識にご参考ください🙂

※このページでは『Google』2023年2月時点における検索数を参考にしています。

暮らしの中にちょっとした笑顔を。『ふわっとスマイル』当サイトにお越し頂きありがとうございます!しか言えない私たちは1記事ずつ精一杯書かせて頂きますm(_ _)m
ことわざ検索数第1位!33100件

最初に発表~栄えあることわざ検索数第1位!
情けは人の為ならず
他人のために親切な想いを寄せたり配慮をすることが、自分自身にとっても良い結果を生むということです。
例えば、他人を助けることで、その人から感謝されることがあります。また、自分自身が困難な状況に陥ったときに、他人が自分を助けてくれることがあるかもしれません。このように、自分自身が思いやりや配慮を示すことで、他人からの援助を得ることができる可能性が高くなるということです。
この言葉は、日本の伝統的な価値観である「和」や「おもてなし」を表現しているとも言われています。人間関係や社会全体において、互いに思いやりを持ち合うことで、より豊かな関係や社会を築くことができるという考え方です。
<例文①>
見放す教師が多い中、彼の担任Aだけはずっっっと怒り、励まし続け見放さなかった。
時は立ち、少ない年金生活で苦しかった担任Aはヤン男が経営する会社で無理なく働いている。
担任Aの気遣い~情けは人の為ならず~は10年以上の時を経て立証された。
<例文②>
速男:(ハァ…さっき現国で”情けは人の為ならず”ってハァ…習ったな…ハァハァ)
新記録の走りを見せていた速男だったが、足を止めそっと手を差し出し遅男を起こしてあげた。
レース終盤、最後の踏ん張りを見せる速男に、2週遅れの遅男が駆け寄り『頑張れぇぇぇ!!』と背中を押した。
速男はコケた。情けない姿で。顔面から。
その日、速男の情けは、遅男の謝罪と普段高くて手の出ないランチ定食Zを得た😀(遅男のオゴリで)
<例文③>
ガリ夫:(情けは人の為ならずって昨日ブログで見たなぁ…)優しいガリ夫は、お腹は減っていたが2つクリームパンをあげた。
…夕方
デブ夫母:『あんた!今日弁当忘れて!お昼どうしたの!?』
デブ夫:『ガリ夫君がクリームパンを2つもくれた』
翌日、ガリ夫の家にはクリームパンが10個届けられた。
ガリ夫の優しさは5倍になって返ってきた(同じ味そんな食べへん…)
ことわざ検索数第2位!22000件

続く第2位~月間検索数第22000件のことわざとは?
花より団子
つまり、外見や装飾よりも実用性や機能性を重視することを示しています。
この言葉は、日本の伝統的な文化やライフスタイルに深く根付いている考え方であり、例えば、料理や食べ物においては、見た目よりも味や栄養価を重視することが重要であるとされています。また、生活用品や衣服などにおいても、実用性や耐久性を重視する傾向があります。
この言葉は、美しいものや外見にこだわることが重要視される現代社会においても、まだまだ通用する考え方であると言えます。外見や見た目よりも、実用性や機能性を重視することが、より豊かで充実した生活を送るために必要なことであると考えられています。
Bread is better than the songs of birds(鳥のさえずりよりもパンの方がいい)
<例文①>
思春期で身なりを気にしだした僕に一喝!『あんたは見た目より中身を鍛えなさい!アホンダラ!』
まぁそうだねと内面の大切さも多少理解した僕に後日、オカンが買ってきたのが花柄Tシャツ。
中身もしぼむって…。(どこに売ってたの?)
<例文②>
彼氏:あれは字が違うよ。本当は『花より団子』で意味は〇△□……。
彼女:そうなんだぁ~でも松潤は外見も中身も整ってるよね~。
彼氏:(嵐ファンになっちゃったんだなぁ…)
ことわざ検索数18100件
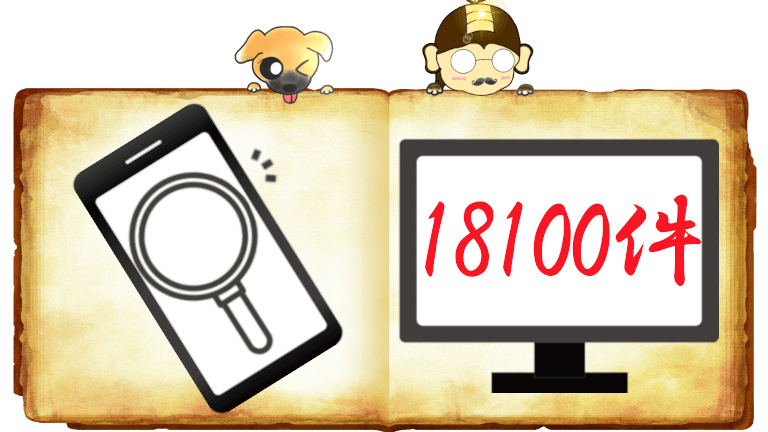
まだ多い検索数!月間約18100件ググられていることわざを見ていきましょう。
覆水盆に返らず
文字通りの意味は、「水を覆した盆は元に戻らない」というものです。
失敗や過ちを犯した際に、その影響が永遠に消えないことを表しています。一度起こったことは、どんなに後悔しても、もう取り返しがつかないということです。
このことわざからもわかるように、失敗を未然に防ぐことが大切です。しかし、万が一失敗してしまった場合には、すぐに立ち直り、次につなげるために必要な教訓を得ることが重要です。
<例文>
フラ子:私がイケなかったの…。彼のコト疑って縛り付けて文句言って往復びんたして…。
励子:(うん。アンタが悪い)でもさ、覆水盆に返らずっていうじゃん?また新しい恋を探せばいいじゃん。
フラ子:こぼれた水を戻して彼と復縁できるなら、いくらでも戻すわよ!ヘラとスコップ買ってきて!
励子:誰が行くかアホンダラ!自分で買ってこい!
三つ子の魂百まで
子供時代の経験や教育が、その人の性格や行動に大きな影響を与えることを表す。
人は幼い頃に形成された性格や価値観を、大人になっても変えることが難しいということです。
このことわざは、子育てに対しても重要なメッセージを含んでいます。子供の教育は、長期的な視野で行うことが必要であり、幼い頃の環境や経験が、その子供の将来に大きな影響を与えることを示唆しています。したがって、子供たちにとってプラスとなる環境や経験を提供し、良い影響を与えることが大切であると言えます。
この言葉からもわかるように、人間は幼い頃から教育を受け、そこで培った性格や価値観が、その後の人生に大きな影響を与えることが多いと言えます。したがって、子供たちには、良い環境や経験を提供し、良い教育を施すことが必要です。
子供は大人の父
・Old habits die hard.
古くからの癖はなかなか直らない。
・the leopard does not change its spots
豹はその斑点を変えない
・What is learned in the cradle is carried to the grave.
ゆりかごで学んだことは墓場まで運ばれる。
<例文>
名人:いいですか?三つ子の魂百までと言うことわざがあります。この言葉が示すように、あなたが幼い頃に純粋な心・感性で得た数々の”出来事”によって今のアナタは形成されているのです。子供の頃、夢中になった事は何ですか?もう待ちきれない!早く授業終われ!…とワクワクしながら取り組んでいたモノは?そこに鍵が隠されているのです。虫が好きだった人は昆虫博士に、絵本が好きだった人は漫画家に、レゴが好きだった人は建築家にetc…。
迷人:(話長ぇ…)
名人:ちなみに私は『島を冒険すること』です。
迷人:(あんた高橋名人か…)
子供がどこの島を冒険できたんだと突っ込みたくなる迷人さんでした。
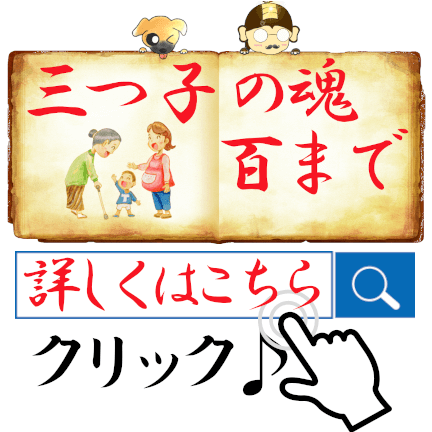
ことわざ検索数14800件
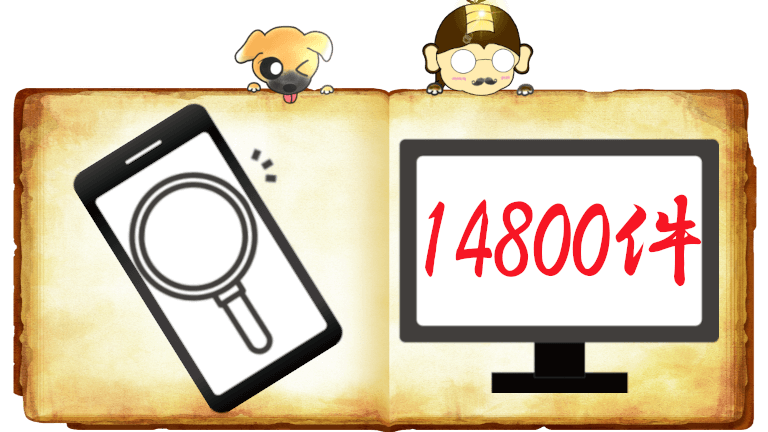
まだまだ多い!月間約14800件ググられていることわざを見ていきましょう。
虎の威を借る狐
具体的には、チカラのある人物や権力者にすり寄り、自分もその威光や力を借りて利益を得ようとする人を指します。
このことわざは、『戦国策』の寓話に由来してます。※詳細にて紹介しています。
この言葉は、悪い意味で使われることが多く、自分自身の力や実力を持たない人が、他の人の名声や権力を利用して自分を強く見せようとする行為を批判する意味でも使われます。しかし、場合によっては、強い力を持つ人と提携することで、自分自身も発展することができる場合があります。そういった場合には、このことわざを使って、自分自身の立場や信念を忘れず、バランスの取れた行動を心がける必要があります。
羊の皮を着た狼。
・A fox that borrows the authority of a tiger.
虎の威を借る狐。(直訳)
・Person who swaggers about under borrowed authority.
借りた権威の下でふんぞり返っている人物。
<例文>
へコ太:はい!部長!お昼ご飯ですね!いつもの牛丼大盛り買ってきます。
へコ太:(飲み会にて)おい平凡同期ども~俺は社長たちに気にいられてるんだぞ♪
同期ども:(わかりやすい虎の威を借る狐野郎だな)
後々、へコ太のあだ名は『FOX』と命名された。
無いものねだり
今の自分にはない、実現・取得率が低いモノを欲しがること。高望み。
自分が持っていないものや、手に入らないものを欲しがり、現実的ではない望みを抱くことを指します。
日本のことわざであり、古くから伝わっています。現代の生活においても、物質的な豊かさが求められるようになり、多くの人々が自分にはないものを欲しがるようになりました。しかし、自分にはないものを追い求めることで、現実から目をそらしてしまい、満足感や幸福感を得られなくなってしまうことがあります。
このことわざは、自分自身の持っているものに感謝し、現実的な望みを持つことが大切だということを教えてくれます。自分にはないものを欲しがること自体は悪いことではありませんが、現実的な目標を持ち、自分自身の努力で手に入れることを心がけることが大切です。また、自分が持っているものを大切にし、それに感謝することが、幸せな生活を送る上で重要なポイントとなります。
非現実的な期待
・asking for the impossible.
不可能を求める
<例文>
太男:俺がキムタクのような顔だったら、もっと痩せてみせるのに。。
ガリ男:僕がもっと太れたら、白鳳も倒して見せるのに。。
厚子:私が石原さとみのような顔だったら化粧代が安くつくのに。。
先生:はい。無いものねだりしてないで勉学に励みましょう。
ことわざ検索数12100件
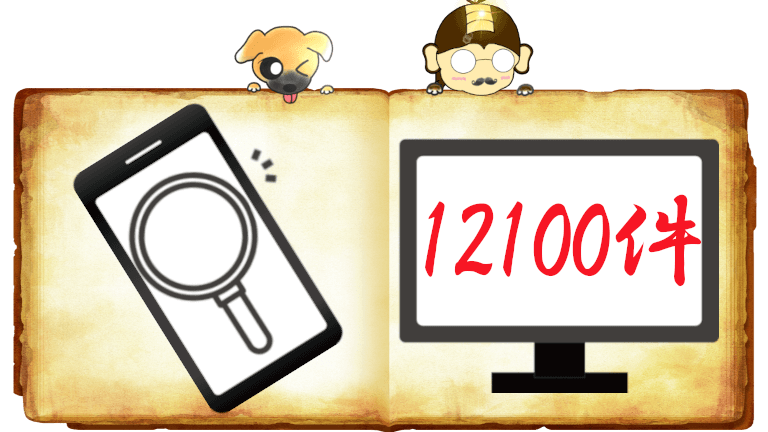
まだまだまだ多い!月間約12100件ググられていることわざを見ていきましょう。
石の上にも三年
(石の上でも三年続けてすわれば暖まるとの意から)
辛抱すれば必ず成功するということわざ。
引用元: 広辞苑 第四版
三年という長い期間で辛いことは幾度となくあれど、負けない事・投げ出さない事・逃げ出さない事・信じぬく事が1番大事だという意味も持ちます。
石の上にも三年(直訳)
・Perseverance will win in the end.
忍耐は最終的に勝利となる
・Perseverance kills the game.
忍耐が獲物を仕留める
<例文>
荒子:何ゆってんのよ!あんたまだ1年目でしょ?あんたが大好きなマイケルジョーダンなんて優勝までに7年もかかってるのよ!それに比べたらアンタなんか屁よ!石の上にも三年、もしくは7年辛抱してみなさいよ!この屁!クサい空気野郎!
忍太:(誰が屁じゃボケ喧嘩売っとんのかワレ!お前クチ悪すぎるんじゃ何 空気扱いしとんねんコラどついたろか……忍耐忍耐…)そうやな。もっと頑張ってみるわ。
気性の荒い荒子の励まし?にも耐えハードな仕事も辛抱し無事に出世した忍太は空気扱いされなくなった。
犬も歩けば棒に当たる
物事を行う者は、時に禍にあう。
また、やってみると思わぬ幸いにあうことのたとえ。
(前者が本来の意味と思われるが、のちの解釈が広く行われる)
引用元: 広辞苑 第四版
- 行動していると禍(わざわい)に遭遇する
- 行動し進んでこそ幸いに巡りあう
犬はワンワン!ガルガルゥ~と吠えては動き回るので、時には棒で殴られたり投げつけられたりするという事から『禍が生じる』という意味を持ちます。
しかし、そうやってキャンキャンクゥ~ンと歩き回ってこそ(棒だけではなく)幸運にも巡りあえるという事も示唆しています。
要約すると
という意味です。
苦労あってもめげずに頑張れ!という励ましことわざです。
もし犬が歩き続ければ棒に当たる(直訳)
・The dog that walks finds the bone.
犬も歩けば骨を見つける(アメリカでは犬には骨という組み合わせが風習であるため棒ではなく骨が用いられる)
・A flying crow always catches something.
飛んでいるカラスは、いつも何かを捕まえる。
他にも『転石苔を生せず~A rolling stone gathers no moss.』転がる石はコケが付かないということわざを表した英語表現も例えとして用いられる場合があります。
<例文>
きゃん子:何ゆってんのよ!あんたまだ2年目でしょ!犬も歩けば棒に当たるってことわざ知らないの!?ここで行動するのをやめてどうすんのよ!上司にシッポフリフリ回してエサでも貰いなさいよ!犬を見習え!この犬!犬!ドッグ野郎!
犬男:(誰がドッグ野郎じゃボケ!キャンキャン吠えまくってるお前こそ犬やろがぃ!このメスドッ……グっ…我慢だ、、)そうやな。もっと行動してみるわ。
気性の荒いきゃん子の励まし?に我慢した犬男は限界突破し、上司と飲み仲間になり仕事を貰え売上を20%伸ばした。
急がば回れ
危険な近道よりも、安全な本道をまわった方が結局は早く目的地につく意。
成果を急ぐなら、一見迂遠(うえん)でも着実な方法をとった方がよい。
※迂遠⇒まわりくどい様。遠回りなさま。
引用元: 広辞苑 第四版
v>
直線的なルートを急いで進むよりも、迂回路を選んで冷静に進んだ方が結果的に早く目的地に到着できるということから生まれました。
急いで行動することが間違っているわけではないが、それが大事なことを見落としたり、誤った行動を起こしたりする可能性があるということを教えてくれます。慌てずに冷静に考え、適切な方向に進むことが重要であるということです。また、あまりに焦ってしまうと、結果的に遠回りをしてしまい、時間やエネルギーを無駄にしてしまうこともあるため、効率的な行動のためにも冷静な判断をすることが大切です。
もしあなたが急いでいるなら、方向転換せよ
・More haste, less speed.
もっと急ぎたいなら、スピードを落とせ。急いでしまうと、作業スピードは落ちる。
・Slow and steady wins the race.
ゆっくり安定していれば、レースに勝つ。
<例文>
回子:何ゆってんのよ!あんたもう3年目でしょ!急がば回れってことわざ知らないの!?今までやってきた事を生かしてミスなく案件こなしなさいよ!パッパとやってしっかりした案件報告ができるわけないでしょ!却下されて作り直しになったら〆切過ぎちゃうじゃない!バビディみたいな事言ってんじゃないわよ!このパッパラパ~!パッパラ男!パ~男!パオが!
急男:(誰がバビディじゃボケ!俺はあんなシワくちゃ妖怪ちゃうわ!パオってなんじゃい!どついたろ…急ぐな急ぐな…)そうやな。ミスしないようキッチリ案件作っていくわ。
ドラゴンボール好きの回子の励まし?に急くことなく、急男はしっかりとした案件を提出し高く評価された。
鬼に金棒
たださえ勇猛な鬼に金棒を持たせる意から、強い上にも強いことのたとえ。
引用元: 広辞苑 第四版
- 鬼は素手でも十分に強い
- そんな強い鬼が金棒を持つとより強き存在になる
- 強きモノがより有効となるツールや手段を手に入れる事
才能や技能に優れた人が、更に優れた道具を手に入れることで、より一層素晴らしい仕事を成し遂げることができるという意味を持ちます。
鬼と金棒(直訳)
・That makes it double sure.
そのおかげで確実性が倍になる
・Adding wings to a tiger.
虎に翼を与える
<例文>
のび太:へぇ~何するの?サッカー?野球?バスケ?
ジャイアン:キックボクシング。
のび太:(…鬼に金棒だな)
スモールライト無しでは、一生この男には勝てないだろうと再認識したのび太であった。
釈迦に説法
よく知っている者になお教えること。
説く必要のないたとえ。
引用元: 広辞苑 第四版
釈迦(仏教の開祖)は教えを説くことで有名であり、その専門分野について多くの知識を持っていたとされています。一方で、専門家である相手に自分が無知であることを露呈してしまい、逆にその相手から教えられてしまうことを表しています。
このことわざは、専門家である人に教えられることがあることを示しています。また、過剰な自信や自己中心的な考え方が誤った結果を招くことがあるということをも表しています。学ぶことや他人の意見を尊重することが、より良い結果につながる場合があるということを教えてくれます。
釈迦に説法(直訳)
・Don’t teach your grandmother to suck eggs.
おばあさんに卵のすすり方を教えてはいけない
<例文>
筋子:うるさいわよ!釈迦に説法って言葉知らないの!?私を誰だと思ってるのよ!筋トレインストラクターよ!筋トレは毎日したらいけないのよ!超回復っていう期間があってその間は筋肉を休めなきゃいけないの!昨日今日始めたガリガリ野郎が得意げに息巻いてんじゃないわよ!アイスでも食っとけ!このガリ男!ガオ!ガオ~ンが!
細男:(誰がガオ~ンじゃ!俺は猛獣か!昨日今日じゃないわ!明日で一週間じゃ!アイス買ってこ…いや、俺の負けだな…)すみませんでした。超回復って何ですか?
こうして筋子の教え?によって効率的な筋トレ方法を学んだ細男はガリガリ体系を卒業した。
人事を尽くして天命を待つ
人間として出来るかぎりのことをして、その上は天命に任せて心を労しない
引用元: 広辞苑 第四版
- やれるだけやる、出来るかぎりの努力をする
- それにまつわる結果は天命に任す
- やれるだけやった後は天に任せ、心を疲れさせない
ベストを尽くして運命を待つ
・God helps them that help themselves.
天は自ら助くる者を助く
・Do the best you can and leave the rest to God.
できる限りベストを尽くして、あとは神に委ねよ
・Man proposes,God disposes.
人が計画し、神が成敗を決める
・To err is human,to forgive,divine.
過ちは人の常、許すのは神の性
<例文>
天子:アンタは食べるという人事を尽くしてるから太るという天命がすぐに押し寄せてきてるじゃない。人事を尽くして天命を待つの最短例でわかりやすい例だわ。
パク太:俺、数日に1回は1kmも走ってんだけどなぁ。。(パクパクグビッと)
天子:うん(人事を尽くして天命を待つの)最長例というか悪しき例として周りにも紹介しやすいわ。一生太るという天命に追われてろ。
立つ鳥跡を濁さず
引き際がいさぎよくキレイな事を例えた意味を持つ。
この言葉は仕事関連、退職時や転勤・転退職といった時に使用される事が多いことわざです。
また転居といった場合にも~鳥が自分の巣は汚さないように~清潔さを保って立ち去る事が大事だという教えでもあります。
そうした場合に使われる頻度が多いことわざですが、意味を要約すると
という意味を持ちます。
立つ鳥跡を濁さず。
・It’s an ill bird that fouls its own nest.
自分自身の巣を汚す鳥は悪いトリだ。
・Leave everything neat and tidy when you go.
あなたが出発する時はすべてのものをキッチリ綺麗にせよ。
失恋励まし中
厳男:お前は鳥以下か!
フラ太:はっ?
厳男:失恋ソングばっかり聴いて涙流して。昔の彼女ばっかり思い出してんと次行けや!立つ鳥跡を濁さずって知らんのか?想い出は綺麗に整理して新しい世界へ飛び立とうや!それができない今のお前は鳥以下やで?
ほら、から揚げ君おごったるから悲しむ自分を食べるつもりで生まれ変われや。
フラ太:(なんか例えが上手いような、そうでもないような)…パクパク。
蓼食う虫も好き好き
辛い蓼を食う虫もあるように、人の好みはさまざまである。
引用元: 広辞苑 第四版
- 人それぞれ、好んでいるものは違う
- 自分の好きなモノが万人受けするわけでは無い
- 人の感性は大なり小なり違うものである
人おのおの好みあり
・So many men,so many opinions.
人それぞれ、意見や考え方がある
・There is no accounting for tastes.
人の好き嫌いはわけのわからないもの
・Tastes differ.
人それぞれに好みが違う
ドラマのバトル
ドラ子:ねぇねぇ?前にお勧めしたドラマどうだった?涙が洪水のように溢れ出たでしょ?
別男:いや、別に。。1mmも涙は出んかったけど。
ドラ子:信じられない…感性腐ってるんじゃない?
別男:いや、あのな。蓼食う虫も好き好きって言ってな。人によって好き嫌いは違うねん。それ以上にお前は大好きな小栗旬に感情移入しすぎたんちゃうか?
ドラ子:そんなんじゃないもん!旬クンが恋に破れて最後泣き崩れてる姿を見て泣かない人がいるなんて考えられないわ!あんたの涙腺腐ってんじゃない?
別男:いや、あのな。。俺は恋愛ものはあんま好きじゃないからさ。アクション系が好きやからさ。
ドラ子:信じられない…。恋愛感情が腐ってんじゃないの?小栗ファンはみんな泣いてるのに。
いや、あのな。。。を腐らず繰り返す別男でした。
七転び八起き
人生において失敗や挫折がつきものであることを示し、それらに打ち勝つために、あきらめずに立ち上がり続けることが重要であると教えてくれます。
人生は何度も失敗することがあるものであり、挫折や苦難が訪れることもありますが、それらに負けずに、何度でも立ち上がり、前に進むことが大切であるとされています。根気強く努力を続けることが、成功に近づくための鍵であることを示しています。
成功者の言葉
私は幾度となく失敗を重ねてきた。
7回どころじゃない。小さなミスから大きなモノまで100回以上は挫折してきた。
8回どころではない。『今回もダメか…』そんな絶望感にとらわれる時はあれど、何度もなんども立ち上がってきた。
ただ『7』には多様なという意味や、聖なる数字という意味合いが、『8』には末広がる幸福という意味が表現されている数字だと旧約聖書などには記されている。
だから私も気持ちよくこの言葉を使おう。
七転び八起きの意味や教訓を胸に刻み、諦めずに夢を手に入れよう。
七転び八起き(直訳)
・Always rising after a fall.
何事も落ちたあとに、いつものぼるもの。
・Never giving up.
諦めない
寝耳に水
この表現は、寝ている時に突然水をかぶせられるという予期せぬ出来事を例えているとされています。何も知らない状態でいきなり出来事が起こると、その衝撃に驚きや混乱を覚えることがあります。
予期せぬ出来事に対する驚きや混乱を表すだけでなく、事前の準備不足や情報不足などが原因で起こる問題にも関連しています。何かを成し遂げるためには、適切な準備が必要であり、情報を収集し、周囲の状況を把握することが重要です。それによって、予期せぬ出来事に対する対応が可能になるため、この言葉は準備の大切さを教えてくれます。
馬子にも衣装
外見の美しさや身なりについてではなく、人間としての品格や精神的な豊かさが大切であることを教えています。物質的に豊かではなくとも、自分の立場にふさわしい姿勢や心を持ち続けることが、人間的な価値を高めることにつながるとされています。
ことわざ検索数9900件
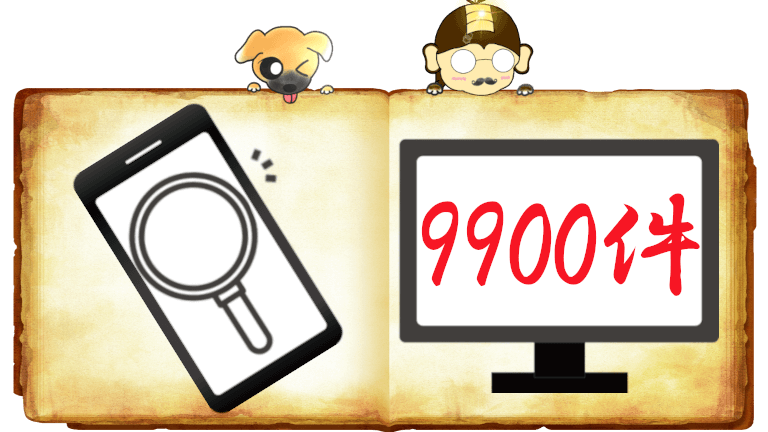
まだまだまだまだ多い!月間約9900件ググられていることわざを見ていきましょう。
馬の耳に念仏
説明をしても理解してもらえない場合や、助言をしても受け入れられない場合などに用いられます。
この言葉は、馬が念仏を聞いても理解できないということから来ています。馬は人間が話す言葉を理解することはできませんので、何を言っても無駄であるということが表現されています。
馬の耳に念仏(直訳)
・To preach to deaf ears.
耳が聞こえないものに説教をする
・Talking to a brick wall.
レンガに話しかける
・A nod is as good as a wink to a blind horse.
目の悪い馬にはうなずいても目配せしても効き目はない
・There’s none so deaf as those who will not hear.
聞こうとしない人が最も耳の悪い人
言葉のムチ
馬太:(ゴクゴク)かぁ~!やっぱ仕事終わってからのビ~ルはウマいねぇ~!
ムチ子:(パチィ~ン!)何が『かぁ~!』よ!今日アンタ禁酒日でしょ!?週に1回は休肝日作れって言ったじゃない!ほんと馬の耳に念仏ね!馬ヅラでウマいねぇ~とか上手いこと言ってんじゃないわよ!馬を見習って走ってこい!このウマヅラ野郎!
馬太:(うるさいんじゃ!何回ウマってゆうねん!念仏どころか、ただの罵倒やないかい!念仏なら今日も仕事してきた俺をもっと優しく諭さんかい!んで引っぱたくな!だいぶケツ痛いわ!俺を馬に仕立て上げすぎなんじゃこのボ……けど禁酒日に飲んでる俺が悪いか…)明日、休肝日にします。
こうして念仏?だけでなく言葉のムチによって諭された馬太は翌日ビ~ルを飲まずランニングした。
王様の耳はロバの耳
地位や権力があるからといって、すべてを知っているわけではなく、身分が低くても重要な情報を知っている場合があるということを意味しています。
この言葉は、古代ギリシャの哲学者プラトンが記した寓話「国王と騾馬(ロバ)」から来ています。この寓話では、国王が騾馬に様々な質問をしましたが、騾馬は答えられず、国王は騾馬の耳を引っ張って「君は答えないのか?」と言います。すると、騾馬は「あなたが国王であるという理由で、答えられると思ったのですか?」と反論します。つまり、地位や権力によって物事を理解できるわけではないということを示唆しているのです。
果報は寝て待て
幸運は人力ではどうすることもできないから、
あせらないで静かに時機の来るのを待て。
引用元: 広辞苑 第四版
- 幸運は人のチカラで早めたりする事はできない。
- ただ焦らずに努力を重ねていればいつかは報われる
- その時が来るまで落ち着いて頑張る日々を過ごしていこう
この言葉は、中国の古典である「孟子」にある一節から来ているという説があります。孟子は、「善を行えば必ず報いがあるが、時期は遅くとも必ず訪れる」と述べています。つまり、善行を行った人は、その報いが必ず自分に返ってくるということを意味しているのです。
「果報は寝て待て」は、自分が努力していないのに報われるという意味ではなく、良い行いをしたことがある人が、その報いを受けるために、ただ何もしなくてもいいということを表しています。また、報いが自分に返ってくるまで、落ち着いて待つことが大切であるということも含んでいます。
待つ人には何でもやってくる
・There is luck in leisure.
暇な時に幸運は訪れる。
・Grin and bear it.
笑って耐えよ。きっといいことがある。
寝ろver
焦男:なぜだ…なぜ俺は仕事で成功できない?俺の努力が足りないからか?寝る間も削って頑張ってるのに。。
寝子:う~んとね、多分アンタ寝てないから効率悪いのよ。1日4時間しか寝てない?だから肉体的にも精神的にも不安定で作業効率が落ちてるのよ。果報は寝て待てって言うでしょ?あんたの場合本当に寝た方が良いわよ?
焦男:でも怖いんだ…もっと頑張らないと!そう思うといてもたってもいられないんだ…。
寝子:う~んとね、ビル・ゲイツもジェフ・べゾスも睡眠の大切さを主張してて、7時間キッチリ寝て仕事の作業効率を下げないようにしてるの。あんたみたいに焦って毎日を過ごしていると成功もビビって逃げちゃうわよ?いったん落ち着いて睡眠時間増やせば?
焦男:わかった。(グゥ~スカピぃ~)
即寝してんじゃね~よと寝子に思われながら、焦男は睡眠時間を増やした結果メンタルも安定し作業効率を上げ小さな成功がポツポツと生まれ更なる精を発揮できるようになった。
蛍雪の功
一般的には地味ながら継続的に努力を続けることで、積み重なった努力がやがて大きな成果を生み出すことを表しています。
この言葉の由来は、中国の唐代に活躍した詩人・白居易の詩にあります。彼は「蛍雪の功を認める」という言葉を用いて、青年時代に熱心に学問に励んだ儒者の功績を称えた詩を残しています。蛍雪は、夏の夜に光を放つ蛍と、冬の雪という対象を用いています。これは、蛍が短い夏の季節だけしか生きられないのに対して、雪は長い冬の季節を乗り越えているという点に注目し、それぞれの努力が季節によって異なることを表現しています。
「蛍雪の功」は、人々の心に残るような価値ある行為や努力を意味しており、特に長い年月をかけて積み重ねられた努力がもたらす大きな成果を表現することがあります。
転ばぬ先の杖
前もって用意しておくことで、将来のトラブルや失敗を予防するための手段やサポートを確保しておくことが大切であるということを示しています。
事前に十分な準備をしておくことが、将来に起こりうるトラブルや問題を回避するための杖になるということが表現されています。
リスクを最小限に抑えるために、あらかじめ予測しておくことが大切であることも示したことわざです。
将来の不測の事態に備えることが、成功への道を拓くための大切な準備であるということをも表しています。
転ばぬ先の杖(直訳)
・Look before you leap.
飛ぶ前に見よ~よく考えてから取りかかれ
・Prevention is better than cure.
予防は治療にまさる
プレゼント前
あと1か月後、付き合いたての彼女の誕生日前。
何男:俺は今○○が好きやねんけど、お前はどぅ?そんなに?じゃあコレは?
貰子:う~ん、私はやっぱり□□が好きかなぁ。あっ!あとアレも好き。私の趣味としてはetc…。
何気なく、さりげなく、彼女の好みや趣味を聞き出しどんな誕生日プレゼントをあげるかを前以て考える何男。そして1か月後…。
何男:はい!モアイ像の抱き枕。
貰子:わぁ!ありがとう!よく私がモアイ像大好き人間ってわかったね?
転ばぬ先の杖を実践していなければ、ありきたりな動物の人形をあげるという失敗を犯していたであろう”何男”は貰子の一風変わった好みにも気づいたのだった。
少年よ、大志を抱け
若いうちから自分にとっての大切な目標を見つけ、それに向かって全力で努力することが、将来の自分を作り上げるための重要なステップであるということを示しています。
この言葉は、日本の教育者・福沢諭吉が、明治時代に著した「学問のすすめ」という著作の中で使われたもので、若者が進路や職業を選ぶ際に、自分自身の才能や興味に合った目標を設定し、それに向かって挑戦することを勧めたものです。
「少年よ、大志を抱け」は、若い人たちが自分の才能や夢を見つけることで、自己実現のための力を育てることができることを示しています。また、若いうちから大きな目標を持つことで、自己成長や社会に貢献することができるということをも表現しています。
棚から牡丹餅
直訳すると、牡丹餅が棚から降ってきたように簡単に手に入るということを表現しています。
牡丹餅とは、桜餅のような和菓子で、赤い餡が入った餅のことです。昔の人々は、牡丹餅が非常に高価で、なかなか手に入らなかったため、それを手に入れることが思いがけない幸運であるとされていました。
「棚から牡丹餅」は、現在でも、思いがけず良いものを手に入れたり、簡単に大きな利益を得たりすることを表現するために使われることがあります。ただし、この言葉には、思いがけない良いことがあったとしても、それに甘えて満足してしまうと、それ以上の良いものを手に入れることができなくなってしまうという注意喚起も含まれています。
棚から牡丹餅(直訳)
・windfall
棚ぼた
・He thinks that roasted larks will fall into his mouth
彼は自分の口にヒバリのロースト肉が落ちてこないかと期待している
恋愛編
昔々、日本国内を旅する男がいた。
故郷である広い北海道から、東北・関東・中部・関西・九州にも足を運び、様々な都市の文化に触れ色々な人と巡り合う刺激を求め歩き続けていた。
そんな男は、ある日1人の女性と出会った。
笑顔がキュートでモロ好み。沖縄のゴーヤチャンプル店で働く女性に恋をした。
そんな刺激に打ちひしがれ、彼が漏らした言葉。
男:おぉ…遠い南の島でこのような女性と出会えるとは…。まさに棚から牡丹餅だ。。
多くの読者は思ったであろう。
読者:そこは一期一会じゃね?
何にせよ男は自分の故郷から遠く離れた南の島で、モロ好みな女性と出会うという思いがけない好運に巡りあえたのだった。
猫に小判
貴重なものを与えても何の反応もないことにたとえていう。
転じて、価値のあるものでも持つ人によって何の役にも立たないことにいう。
引用元: 広辞苑 第四版
猫は小判を使うことができないため、どんなに高価であっても無駄な贈り物となります。
この言葉の起源には、江戸時代に人気を博した落語「猫の皿」が関係しています。この落語の中では、猫が偶然にも金平糖を手に入れ、それを皿の下に隠して、自分が眠っている間にお膳を奪おうと企む話が語られます。しかし、猫は金平糖を見つけたときには、自分にとって価値があるものとして認識できず、最終的には皿を壊してしまいます。
このように、猫にとっては意味のないものが、人間にとっては価値があるものであることがあるため、「猫に小判」という言葉が生まれたと考えられています。
このように無駄な贈り物や手間や時間をかけることは避けるべきであるということを示しています。つまり、相手の状況や価値観を理解し、その上で適切な贈り物や対応をすることが大切であるということを示唆しています。
猫に小判
・Really big waste of resources
本当に大きな資力の無駄
・Don’t cast pearls before swine.
豚に真珠を投げるな
I Phone編
電子:母さん!今日iphoneの最新機種が割引価格であって誕生日プレゼントも兼ねて買ってきたよ!
70代母:あらあら、ありがとう。電話はできるの?
電子:当たり前じゃない!番号は○○で、こんな機能があって5G対応で100GB以上の要領があって…etc。
70代母:あらあら、凄いわね。電話はできるの?
電子:……。
猫に小判だったプレゼントは今、家の固定電話の代わりとして活用されている。
美辞麗句
美しい響きを持ち、感性に訴えかけるような言葉遣いや表現を指して用いられます。
この言葉は、元々は古代中国の詩経に登場する「辭美麗而不厭」(言葉が美しく、飽きさせない)という表現から来ています。日本においては、江戸時代の文化が盛んになったころに広まったとされています。
「美辞麗句」は、優れた表現力や感性を持つ人々が作り出す美しい言葉や文章を評価するために用いられます。また、この言葉を用いることで、単に説明するだけではなく、人々の感情を揺さぶる表現をすることが重要であることが示されます。
しかし、美辞麗句を多用することで、本質的な内容が伝わりにくくなったり、軽薄な印象を与えることもあるため、適度に使用することが望ましいとされています。
瓢箪から駒
瓢箪と駒は、形や用途が全く異なるものであるため、予想もつかないような変化を表現する際に使われます。
この言葉の起源は不明ですが、一説によれば、駒が乗るために必要な鞍や手綱を持っていない場合に、瓢箪を使って代用することがあったとされています。瓢箪から駒が生まれたというのは、このような代用品が必要な状況から、思わぬ大きな発展があったことを表現したものと考えられています。
現代では、瓢箪から駒のような意外な展開が起こることがあるため、この言葉は様々な場面で用いられます。例えば、何気ない発言やアイデアが、意外なきっかけとなってビジネスやプロジェクトが大きく発展することがあるとき、瓢箪から駒という表現が用いられることがあります。また、逆に思わぬ失敗やトラブルが起こり、状況が一変することも、瓢箪から駒という言葉で表現されることがあります。
貧すれば鈍する
貧しい環境で生活しなければならない人々は、生活のために働くことが多く、学ぶ時間や余裕がないため、能力や知識が十分に身につかないことが考えられます。
また、貧困はストレスや不安を引き起こすことがあり、集中力や創造力を低下させる原因にもなるため、仕事や学業においても悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、経済的な安定が大切であり、社会的な支援が必要な人々には、貧困から抜け出す機会を提供することが重要とされています。
一方で、「貧すれば鈍する」という言葉は、単なる批判や差別的な意図を持って用いられることもあります。貧困の原因は様々であり、経済的な力が弱いことが自己責任であると考えることは誤りです。社会的に公正な環境を整備することで、貧困を脱する機会を広げることが大切です。
面従腹背
相手には従順に見せかけながら、本音では相手に対する反感や反発を抱いている場合に用いられます。
この言葉は、中国の古典『孫子兵法』に由来する兵法用語であり、戦争においては、敵に対して表向きは降伏を装いながら、実際には反撃の準備をしている戦術を表現していました。また政治やビジネスの世界においてもよく用いられます。
ただし、「面従腹背」が常に悪意を持った行為であるわけではありません。相手との関係や状況によっては、本音を言いづらい場合や、相手に対して不信感を抱いている場合でも、表面上は礼儀正しく接することが求められる場合もあります。しかし、裏での反対行動が問題となる場合もあるため、人との関係を築く上で、相手を欺くような行為は避けるべきです。
類は友を呼ぶ
人間関係において、自分自身と似たような性格や趣味、価値観を持つ人たちと出会うことが多いということを表しています。
この言葉が指すのは、良い方向にも悪い方向にも働く可能性があります。たとえば、優秀な人たちと交友を深めれば、自分もそのような成功を収めることができるというメリットがあります。また、良い友人たちと一緒にいることで、自分自身がよりよい方向に成長することができるという点もあります。
しかし、同様の価値観を持つ人たちと集まることで、自分自身の考え方や行動に偏りが生じる危険性もあるため、常に自己批判的であることが大切です。また、自分自身と異なる考えや価値観を持つ人たちとの交流も積極的に行うことが、自分自身の成長につながるとされています。
ことわざ検索数8100件
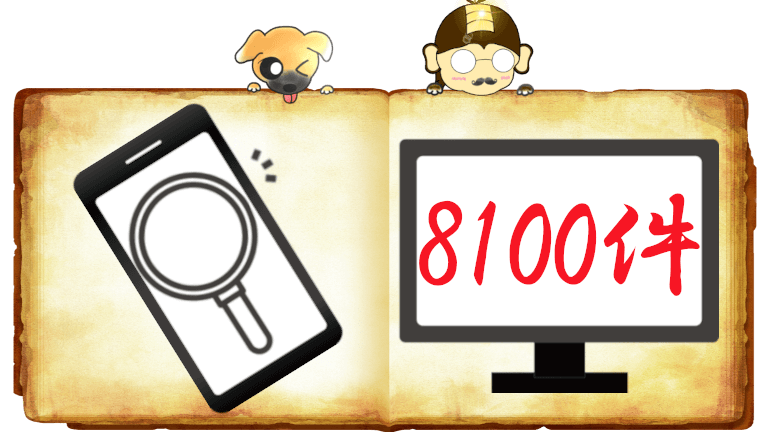
まだまだまだまだまだ多い!月間約8100件ググられていることわざを見ていきましょう。
雨降って地固まる
雨が降ると地面が柔らかくなって、その後に晴れた日には地面が堅くなることを表すことから、苦難に陥っても、頑張って乗り越えることでより強く、堅固な人間になれるということを意味しています。
井の中の蛙大海を知らず
自分の持っている知識や経験がある程度の範囲に限られている人や、自分の生まれ育った地域や文化にこだわりすぎて他の文化や習慣について理解ができない人を指して使われます。このことわざは、自分自身の狭い視野を拡げ、新しいことを学ぶことの大切さを教えてくれます。
石橋を叩いて渡る
例えば、新しい仕事やプロジェクトに取り組む前に、周囲の状況や情報を十分に把握して準備をしておくことが大切であり、その後に行動する際にも細心の注意を払って慎重に進むことが必要です。失敗や危険を未然に防ぐために、慎重かつ努力を惜しまないことの重要性を教えてくれます。
嘘も方便
ただし、このことわざには否定的な意味合いも含まれており、本来は嘘をつくことは避けるべきであるという教訓が込められています。
この言葉は仏教の教えから派生したもので、時には真実を隠してでも、人々を救済することが重要であると教えています。ただし、現代では、嘘をついて他人を欺くことは非倫理的であると考えられているため、嘘も方便を悪用することは避けるべきです。
河童の川流れ
「河童」とは、日本の伝承上の妖怪の一種で、水辺に住むとされています。このことわざは、河童という川に住む生き物が、自分たちの生活や習慣に合わないような予期しない出来事が起きた場合、それに対処することができずに流されてしまうことを表しています。
人生において予期しないことが起こることを覚悟し、それに備えることが大切であるという教訓を示しています。また自然や環境に対する畏敬の念や、謙虚さが重要であるということも感じ取れます。
木を見て森を見ず
つまり、細かいことばかりにこだわって、大局的な視点を持てずにいると、本質的なことや全体像を見逃してしまうことになります。
例えば、仕事においては、細かい部分にこだわりすぎて全体の進捗や目的を見失ってしまうことがあります。また、人間関係においても、些細なことにこだわりすぎて、大切な人間関係やコミュニケーションが崩れてしまうことがあります。
このことわざからは、全体像や大局的な視点を持ち、物事を客観的に見ることの重要性が示されています。また、些細なことに囚われず、本質的なことを見極めることが大切であるという教訓も含まれています。
恋は盲目
つまり、恋愛感情が強くなると、自分自身が冷静な判断ができず、相手の欠点や問題を見落としてしまうことがあります。また、周りからのアドバイスや警告を無視し、相手に熱中してしまうこともあるかもしれません。
恋愛においては熱狂的な感情に振り回されず、冷静な判断力を持つことが大切であるという教訓が示されています。また、恋愛においては、自分自身を客観的に見つめ、相手の本当の姿を見極めることも必要です。
失敗は成功のもと
失敗をすることで、自分自身や取り組んでいることについて学び、経験から得られた知識や教訓を生かし、新しいチャレンジに挑戦することができます。
失敗を恐れずにチャレンジすることが重要であるということが示されています。また、失敗をすることが悪いことではなく、成功に向けたプロセスの一部であるという前向きな姿勢が重要であるという教訓が含まれています。
賽は投げられた
何かを決断したり行動したりした後には、それに関する結果は既に決まっているので、結果に対して悔やんだり後悔することはできません。自分の決断や行動に自信を持ち、結果に対して受け止めることが大切であるということを示しています。
自分自身が決断を下し、行動を起こした場合には、その結果を受け止め、次のチャレンジに向けて前向きに取り組むことが重要であるという教訓が示されています。また、何かを決断する際には、よく考え、慎重に判断することが必要であることも示されています。
触らぬ神に祟りなし
自分自身に関係のない問題や他人のプライバシーに干渉することは、思わぬトラブルやトラブルの原因になる可能性があるということを示しています。また、自分自身にとって本当に重要な問題にだけ集中し、他人には干渉せず、彼らの選択や意見を尊重することが必要であることを示しています。
このことわざは、他人とのコミュニケーションにおいては、相手の意見や立場を尊重し、自分自身が関わる必要のない問題については、積極的に関わらない方が良いという教訓が示されています。また、自分自身にとって本当に重要な問題に集中し、自分自身の責任を果たすことが大切であることも示されています。
知らぬが仏
不要な情報や知識にとらわれることは、精神的な負担を引き起こし、ストレスや不安を増幅する可能性があるということを示しています。また、何かを知ることが自分自身や他人にとってプラスの影響をもたらす場合には、それを積極的に知ることが大切であるという意味も含まれています。
知識や情報を得ることの重要性が示される一方で、不必要な情報に縛られることがストレスを引き起こす場合には、無知であることが幸せにつながることもあるという教訓が示されています。また、知る必要のないことに無駄な時間や労力を費やすことは避け、自分自身や周囲の人々にとって価値のある知識を追求することが大切であることも示されています。
時は金なり
時間の価値を認識することの重要性が示されます。時間は有限であり、一度過ぎ去ったら戻ってこないため、有意義に使うことが大切です。また、時間は金銭以上に貴重であるため、無駄な時間を過ごしたり、大切なことを後回しにすることは避けるべきであり、自分自身や周囲の人々のために有益なことに時間を費やすことが重要であることが示されています。
時間の大切さを再確認し、自分自身の時間の使い方を見直すことが必要であることが示されます。時間を無駄に過ごさず、自分自身や周囲の人々のために有益なことに時間を費やし、充実した人生を送ることが大切であることが示されています。
糠に釘
「糠」は、米を精米した際に出る外皮のことで、食用にはなりません。一方、「釘」は、建物や家具などを作る際に使用される金属製の留め具であり、糠に釘を打つことは、全く異なる物質同士を強引に結びつけようとしていることを意味しています。
このことわざからは、不適切な手段で問題を解決しようとすることの危険性が示されます。問題を解決するために、正しい手段や方法を選択することが重要であり、不適切な手段で解決しようとすると、逆に問題を悪化させることになる可能性があることが示されています。
問題解決には適切な手段を選択することが重要であることが示されます。問題を解決するためには、事前に情報を収集し、適切な手段を選択することが必要です。また、問題解決には、時間と労力が必要であり、急いで解決しようとして、不適切な手段を選択することは避けるべきであることが伺われます。
能ある鷹は爪を隠す
「鷹」は、優れた能力を持った鳥として、このことわざの中で用いられています。「爪」は、鷹が獲物を捕まえるための重要な器官であり、鷹の「爪」は鷹が持つ能力や技術を象徴しています。
能力や技術を持った人物が、そのことを見せびらかす必要はなく、むしろ控えめであるべきであることが示されています。控えめに振る舞うことで、周りの人々からの信頼や評価を高めることができ、人間関係の構築にも役立ちます。
また、このことわざからは、自分自身の能力や技術を過信しすぎることが、自信過剰や高慢の原因になることも示唆されています。能力や技術を持った人物でも、控えめになることで、常に成長し続けることができます。したがって、このことわざからは、謙虚さや控えめな態度が重要であることが表現されています。
張り子の虎
「張り子」とは、紙や布に張りつけた骨組みのことで、その中に中身がなく、ただ形だけが残っているものです。「虎」は、強さや威厳を持つ動物として用いられています。
見かけや言葉だけで、中身や実力がない人や物事が存在するということが表現されています。見た目だけで判断することは危険であり、本物かどうかを見極めることが必要であるということが示されています。
また見かけだけで勝手に判断するのではなく、実際に物事を見極めることが大切であるという教訓も含まれています。何かに取り組むときは、外見だけでなく中身や実力を見極めることが重要であることが表現されています。
豚に真珠
「豚」は、食用のイメージがあり、物事の価値を見極める力に欠けるとされます。「真珠」は、高価で希少価値のあるものを意味します。
このことわざからは、本来価値が高く貴重なものであっても、その価値を理解できない人がいるということを表しています。また、そのような人が、その貴重なものを手に入れることがあっても、それを活かせないため、無駄になってしまうことが多いとされます。
物事の価値を理解し、それを適切に活用することが大切であることが表現されています。また、自分が知らないことにも興味を持ち、新しいことを学び、知識や経験を積むことで、自分自身の成長につながることができます。
身から出た錆
「錆」とは、鉄や鋼などが空気中の水分や酸素と反応して生じるさびを指します。このことわざでは、悪い行いが自分自身に影響を与えることが、さびが鉄に影響を与えるように、身体に染みつくと表現されています。
自分自身が人に対して正しい行動をとることが大切であることが示されています。また、他人に悪いことをした場合には、それが自分自身に影響を与える可能性があるため、正しい行動をとることが求められます。また、誠実さや思いやりの心を持ち、人に対して良い行動をとることが、自分自身にも良い影響をもたらすことが表されています。
ミイラ取りがミイラになる
このことわざは、エジプトのミイラにちなんでいます。かつて、ミイラは貴重な薬品や死者を弔うための宝物として、探索者たちの熱心な探究の対象でした。しかし、ミイラを取りにいった者が、その罠や病気にかかり、自らの命を落とすことがあったため、このことわざが生まれたとされています。
他人に危害を加えることが、結果的に自分自身に悪い影響を及ぼすことが表現されています。また、自分自身がやりたいことを他人に強制することは、自分自身がその弊害を受けることがあるため、相手に対して思いやりを持って接することが大切であることが示されています。他人に対する危害行為を戒め、自己責任を持って行動することの大切さを教えてくれる言葉として広く知られています。
元の木阿弥
「木阿弥」とは、かつての能楽師であり、演目「松風」の一節「元の木阿弥、いい音出しているか」から転じた言葉です。このことわざでは、一度壊れたものが修復しても元の状態には戻らないという意味で使われます。また、もともとの状態に戻すことができないという意味合いも含まれます。
例えば、失敗をしてしまった場合や物事が壊れてしまった場合に、「元の木阿弥」と表現されることがあります。このことわざからは、失敗や破壊を避けるために、事前に慎重に行動することの大切さや、失敗した場合でも再び元の状態に戻すことができないことを認識する必要があることが示されています。また、物事を大切に扱い、慎重な行動をとることが大切であることも示唆されています。
餅は餅屋
餅を作ることに長けた餅屋が、他のことに詳しいとは限らないということです。自分が専門としている分野においては詳しいが、他の分野については素人であることが多いため、それ以外のことには口出しをするな、という意味が込められています。
例えば、医者が自分の専門分野以外である健康法について語ることは「餅は餅屋」と言えます。自分の専門分野以外のことについては専門家に相談することが大切であるということを意味しています。また、自分が専門とする分野においては、素人からの干渉や評価に惑わされずに、自分のスキルを信じて取り組むことが大切であることも示唆されています。
ことわざ検索数6600件
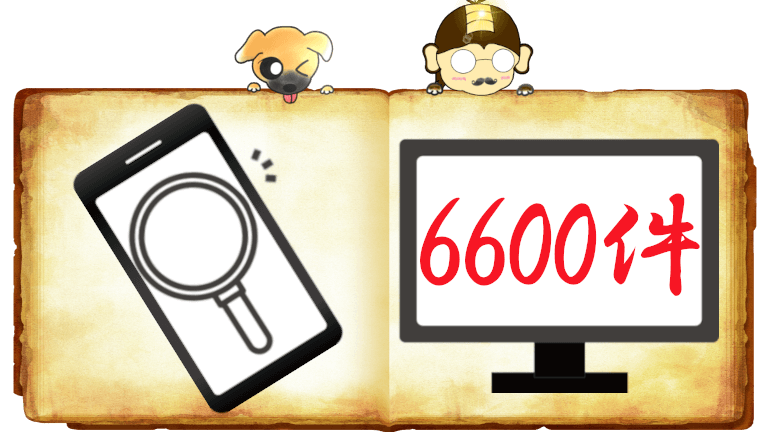
減ってきた…月間約6600件ググられていることわざを見ていきましょう。
青菜に塩をする
小さなことでも真剣に取り組み大切にする姿勢が大切だということを表しています。また、「青菜に塩をする」という表現は、素朴な食材である青菜に、価値を与える行為としても用いられます。
明日は明日の風が吹く
将来に対する計画や予想はあくまでも予測であり、現実には変化する可能性があるということを表しています。そのため、現在できることに全力を尽くし、未来のことには柔軟に対応することが大切だとされています。また、現在に集中し今日を大切に生きるという意味も含まれています。
足元を見る
具体的には、自分の足元に注意を払うことでつまづきや転倒を避けることができるように、自分が直面している現実や問題に目を向け、それに対処することが必要だということを表しています。また謙虚さや謙遜の意味合いも含まれており、自分がどこにいても周りに敬意を払い、自分自身も常に自己反省を行う姿勢が重要であることを示しています。
医者の不養生
医療従事者は、日々多忙な業務に追われる中で、他人の健康に尽くすことが多く、自分自身の健康にまで気を配ることができなくなってしまう傾向があります。そのため、医者や看護師が自分の健康管理を怠ってしまうと、自分自身が病気にかかったり、疲労がたまってしまったりすることがあります。医療従事者が自己管理を怠らず、常に健康的な生活を心がけることが重要であることを表しています。
蛙の子は蛙
具体的には、親が優秀であれば子も優秀になる可能性が高く、逆に親が劣っていれば子も劣る可能性が高いということを指します。また、身分や環境が変わっても自分自身の根源には変わらないという意味合いも含まれています。つまり、どんな環境に置かれても自分自身が持つ本質的な部分は変わらず、自分自身の努力で向上することができるということを示しています。
勝てば官軍、負ければ賊軍
結果がすべてであり、勝つことが最も重要であるという価値観を表しています。しかし、このことわざは、単純な結果主義ではなく勝敗を超えた大局的な視点が必要であることを示唆しています。また、勝者と敗者の判断が常に正しいわけではなく、時には敗者の立場からの見方や意見も尊重する必要があるということも表しています。
かわいい子には旅をさせよ
子どもには自分で考え、自分で行動する力を養うことが大切であり、遠くへ旅行することで新しい経験を積み、自分自身を成長させることができるということを示しています。また親が子どもを愛しているが故に、時には手放し、放っておかなければならないこともあるということも表しています。つまり、子どもには自分で学び、自分で成長する機会を与え、自立させることが必要であるということが表現されています。
五十歩百歩
同じようなこと、同程度のこと、違いがほとんどないことを比較する際に用いられます。例えば、「AとBどちらも同じくらい良い」というように、どちらが優れているわけでもなく、差がほとんどないことを表現する際に使われます。また、「五十歩百歩」という表現は、どちらが優れているわけでもなく、同じレベルであることを示すためにも用いられます。
弱肉強食
強い者が生き残り、弱い者が淘汰されるということで、自然界においてこのような現象が起こることはよく知られています。人間社会においても、強い者が弱い者を支配し、搾取することがあるため、このことわざは社会的な現象を表す場合もあります。ただし「弱肉」と「強食」という単語が含まれており、野蛮なイメージを与えることがこの言葉にはあるため、必ずしも良いことだけを表現するわけではありません。
千里の道も一歩から
大きなことを成し遂げるためには、一歩ずつ着実に進んでいくことが必要であるということです。どんなに遠い場所に行こうとも、最初に一歩を踏み出せば、そこから次の一歩、またその次の一歩と積み重ねていくことで目標に近づいていくことができます。目標達成に向けて、毎日少しずつでも進んでいくことの大切さを示しています。
どんぐりの背比べ
同じようなものを比較する場合に、微々たる差であっても、細かく比較することを非難するために使われます。例えば、同じ種類のどんぐりを持っている人たちが、微々たる差でどんぐりの大きさを比較するのは無意味であるということです。このことわざは、人々が細かいことにこだわりすぎず、より重要なことに目を向けることの重要性を教えてくれます。
長いものには巻かれろ
権力や影響力のある人や組織に付き従うことで、自分自身がその恩恵を受けられる可能性が高いということです。ただし、このことわざには「巻かれろ」という表現が含まれるため、自己主張ができないなどマイナスのイメージを与えることがあります。また、権力や影響力のある人や組織に従いすぎることで、自分自身の判断力が鈍り自己主張ができなくなってしまう可能性もあるため、常にバランスを考える必要があります。
憎まれっ子世にはばかる
才能や能力を持っている人ほど、周囲の反感や嫉妬を買ってしまうことがあるということです。しかし、そのような状況でも諦めずに自分の才能や能力を磨き続け、自信を持って前進することが大切だということも示唆しています。また、反感や嫉妬を買う原因になってしまう自分自身の態度や言動についても、反省し改善することが必要であるということも示唆されています。
不言実行
何かを達成するためには、口先だけでなく、実際に行動して成果を出すことが必要であるということです。言葉ばかりで実行力がない人を批判するために使われることもあります。また、自分自身もこのことわざを念頭に置き、目標や計画を立てたら、実際にそれを実行に移すことが重要であることを意識することが大切です。
踏んだり蹴ったり
自分の意志ではどうにもならない状況に陥り、翻弄されることを意味しています。一度にいくつもの問題やトラブルに遭遇し、どれを優先すべきか分からなくなるような状況にも使われます。また運や状況に左右されず、自分自身の力で乗り越えるためには、冷静に状況を把握し一つずつ解決策を見つけていくことが必要であるという教訓も示唆されています。
焼け石に水
病は気から
心が元気であれば、体も健康である可能性が高く、逆に心が病んでいると、体調も悪くなりがちであることを意味しています。このことわざは、ストレスや精神的な負担が健康に悪影響を与えることを示唆しています。また心身ともに健康を保つためには健康的な生活習慣を心がけ、ストレスを適切に解消することが重要であることが示唆されています。
持ちつ持たれつ
自分が困った時には、友人や仲間が助けてくれるように、また自分自身も誰かが困っているときには手を差し伸べるようにすることが大切であるということを意味しています。お互いに利益を与えることが大切であることを示しています。また、一人で孤立するよりも、人との繋がりを持ち信頼関係を築くことが人生において大切なことであるということも示唆されています。
笑う門には福来る
明るく前向きに生きることで、周りからも好かれ、幸運が訪れる可能性が高くなるということを意味しています。心の持ち方が人生を豊かにすることを表現している言葉です。また人生において困難があっても、常にポジティブな姿勢で向き合い、前向きに努力することが大切であることが示唆されています。その結果、良い結果が訪れる可能性が高くなるということです。
ことわざ検索数5400件
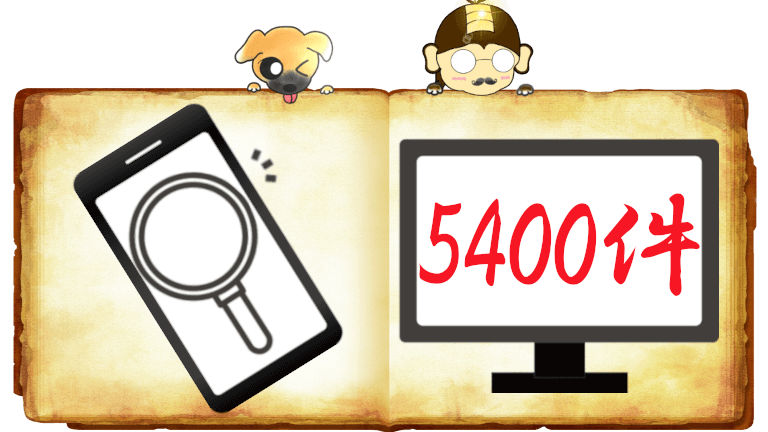
また減ってきた…月間約5400件ググられていることわざを見ていきましょう。
画竜点睛を欠く
もともとは、中国の唐代の詩人、王之涣が詩「登鹳雀楼」の中で、「画龍点睛(がりょうてんせい)」という表現を使いました。これは、絵の最後に龍の目を描くことで、その龍に命を吹き込む、つまり、完成に必要な仕上げの意味を持ちます。
「画竜点睛を欠く」は、この表現から派生した言葉で、何かを作り上げる過程で、最後の仕上げとして必要な要素が欠けている状態を表します。たとえば、文章やプレゼンテーション、デザインや料理など、何かを創作する際に、完成しているようで何かが足りないと感じるときに使われます。
この言葉は、「完成度を高めるためには、最後の仕上げが欠かせない」ということを示しています。仕事や創作活動をする際には、完成度を高めるために、最後の仕上げを怠らずに行うことが大切であるということです。
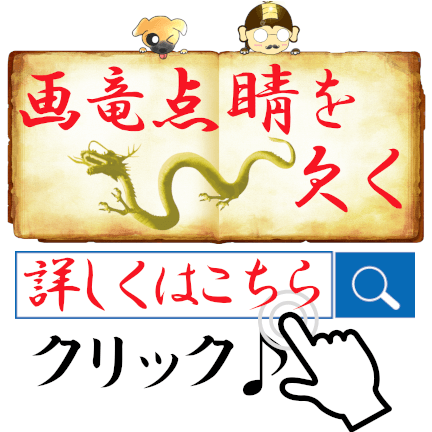
油を売る
火事場の馬鹿力
一般的には、普段は力不足だったり、行動力がなかったりする人でも、火事などの緊急事態が発生すると、人命や財産を守るために、驚くべき行動力や力を発揮することがあります。このような行動力のことを、「火事場の馬鹿力」と表現することがあります。
ただし、この言葉には、馬鹿力という語が含まれているため、ある種の批判や揶揄が含まれているとも言えます。例えば、普段は計画的でなかったり、注意力が足りなかったりする人が、火事場での無鉄砲な行動で逆に事態を悪化させてしまうこともあるためです。
勝って兜の緒を締めよ
「兜」は、武士が戦いに備えてかぶる頭部防具のことで、「緒」は兜の紐を指します。勝利を得ると、人は自信を持って油断してしまいがちですが、それでは再び新たな試練や困難に遭遇したときに備えていないことになります。そのため、「勝って兜の緒を締めよ」ということわざは、勝利を得た後には再び気を引き締めて準備を怠らず、次の試練に備えることが大切だということを示しています。
勝利を得たときには謙虚さを忘れず、常に努力を続けることが重要であることを表現しています。勝利を喜び、自信を持つことも大切ですが、それと同時に、次のステップに向けて準備をし、また勝利を得るために必要な努力を怠らないことが必要です。
猿も木から落ちる
猿は木に登ることが上手であることから、高い場所でも安定しているように見えますが、時にはつまずいたり、手を滑らせたりして、木から落ちてしまうことがあります。このことから、「猿も木から落ちる」という言葉が生まれました。
人間も同じで、優れた能力や技術を持っていても、ミスやミステイクを犯すことがあります。完璧な人間は存在せず、誰でも失敗することがあるため、このことわざは、失敗を恐れずに、挑戦し続けることが大切だということを示しています。
また、「猿も木から落ちる」は、驕りや自信過剰に陥ることがないよう、謙虚さを持って行動することが必要だとも言えます。自分が何かを持っていると思っても、誰でもミスをする可能性があることを忘れずに、常に慎重に行動することが大切です。
善は急げ
良いことをするということは、時には困難であったり、努力が必要であったりします。しかし良いことをするのであれば、できるだけ早く行動すべきだということを示しています。時間が経過することで、良い機会を逃したり、悪い方向に進んでしまうこともあるためです。
また、行動することの重要性を含まれています。善行を考えることは重要ですが、行動を起こさなければ意味がありません。行動しなければ何も変わらないということがあります。したがって、良いことをする場合は、できるだけ早く行動を起こして、良い結果を得ることが大切だということを示しています。
ただし急いで行動することが必ずしも良い結果を生むというわけではないことにも注意が必要です。冷静な判断と計画的な行動が必要な場合もあるため、状況に応じて行動を起こすことが大切です。
大は小を兼ねる
大きなものは、小さなものが組み合わさることによって成り立っていることが多いです。例えば、大きな企業には多くの社員が働いており、社員一人ひとりが小さな役割を果たすことで、企業全体が成り立っています。また、自然界でも、大きな生態系には、小さな生物が関わっており、生態系全体が成り立っています。
小さなものや小さな人物でも、重要な役割を担っているということも含まれます。誰もが自分の立場で大切な役割を持っているということであり、どのような人やものにも敬意を払うべきだという意味も記されています。
また、大きなものを成し遂げるためには小さなことにも注意を払う必要があることを示しています。小さなことを見逃すことが大きな失敗を招くこともあるため、全体を見渡しつつ、細かな点にも目を向けることが大切だということが示唆されています。
塵も積もれば山となる
例えば、毎日少しずつ勉強を積み重ねることで、最終的には大きな知識を身に付けることができます。また、貯金を少しずつ積み立てることで、時間が経つにつれて大きなお金になります。
このことわざは、継続的な努力が重要であることを示しています。一度に大きな成果を出すことができなくても、少しずつ積み重ねることで、大きな成果を得ることができます。また、小さなことが重要である~小さなことを無視してしまうと、最終的に大きな問題を引き起こすこともあるため、全ての小さなことに目を向け、一つずつ積み重ねていくことが大切であるということも意味しています。
目先の結果にとらわれず、将来の可能性を見据え、着実に努力を積み重ねることが大切であることを教えてくれる言葉でもあります。
灯台下暗し
例えば、ある人があることを知らないでいるが、周りの人はそのことを知っている場合、「灯台下暗し」という言葉が用いられることがあります。その人がいる場所に灯台があるのに、その灯台の下で暗いということから、近くのものは見えるが、それ以外のものには気がつかないことを表現しています。
このことわざは、自分自身の欠点や不備に気がつかないことがあることを示しています。周りの人にアドバイスや助言を求めることで、自分自身が気づかなかったことに気づくことができるかもしれません。また、自分がどれだけ知識や経験を持っていると思っていても、まだまだ学ぶことがあるということを示しています。常に謙虚な姿勢で学び、周りの人たちの意見や考えに耳を傾けることが大切だということも教えてくれています。
喉元過ぎれば熱さを忘れる
例えば、試験やスポーツの大会など、激しい競争やプレッシャーにさらされている時には、その緊張やストレスが身体に影響を与え、苦しみを感じることがあります。しかし、それらの試練が過ぎ去り、結果が出た後には、その苦しみや辛さを忘れてしまうことがあります。
一時的な苦しみや辛さがあっても、時間が経てば過ぎ去ることを示しています。また、苦しみが終わった後には、その時の経験から学びを得ることができるかもしれないということも意味します。困難を乗り越えることができたという自信や達成感を持つことができ、それが今後の自分にとっての力となるかもしれないということを教えてくれる言葉でもあります。
ただし、このことわざにはあまりにも辛い苦しみやトラウマとなってしまうような経験をした場合には当てはまらないこともあります。
美人薄命
美しい女性は、周囲から注目されやすく、多くの人たちから求愛されることがあります。そのため、美女はしばしば嫉妬や嫌がらせの対象になったり、利用されたりすることがあります。また、美人であるがゆえに、その容姿が原因で不幸に陥ることもあるかもしれません。
このことわざは、見かけだけで人を判断しないことが大切だという意味が含まれています。美しい容姿は、社会的地位や人気を得ることができる反面、その裏には様々な問題や困難があることを忘れてはいけません。また、人間の価値は容姿だけで決まるものではなく、内面や人格、行動力や才能など、多くの要素が重要な役割を果たすことを教えてくれる言葉でもあります。
後の祭り
「後の祭り」の由来には、神事で神前に供え物を捧げる際に、神に贈るものが用意されず、後になってから贈ろうとしたところ、神は既に去ってしまっていたという伝説があります。つまり、準備不足で神に対する礼儀を守れなかったことが「後の祭り」として残ったということです。
計画や準備が不十分であるため、望ましくない結果が生じてしまった場合に用いられます。何かを行う前に、細心の注意を払って十分な準備をし、失敗を防ぐことが大切であることを教えてくれる言葉でもあります。また、後になってから反省しても、すでに起こってしまったことを変えることはできないため、その場で適切な行動を取ることが重要であることも示唆されています。
三日坊主
「三日坊主」の由来には、江戸時代に医師が推奨した、健康のための運動や食事療法がありました。しかし、多くの人が続けられなかったため、医師は「三日坊主」という言葉を使い始めました。つまり、運動や食事療法を始めたばかりの人は、最初の3日間は続けられるが、その後は中途半端になってしまうという傾向があるということです。
この言葉は、新しいことを始めるときに最初のモチベーションが高まっているときには簡単にやめてしまいがちであることを教えてくれます。長期的な目標を達成するためには、継続的な努力が必要であり、最初の3日間を乗り越えることが大切です。また、何かを始める前に、目標を明確にし、途中で諦めないように計画を立て、自己管理能力を高めることが重要であることが示唆されています。
ことわざ検索数4400件
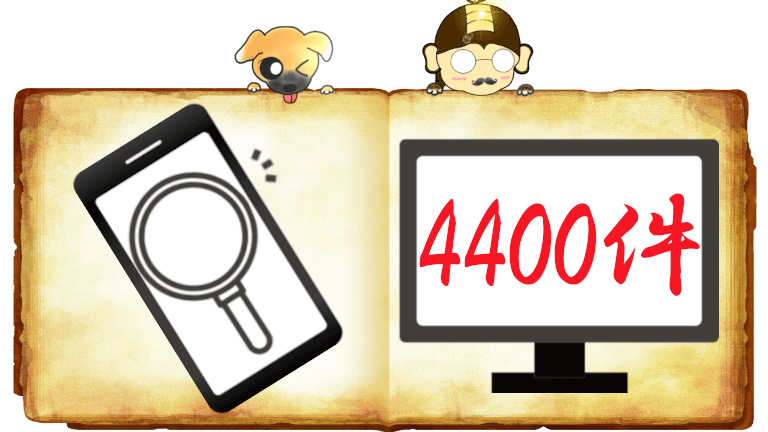
またまた減ってきた…月間約4400件ググられていることわざを見ていきましょう。
言わぬが花
時には口に出すことが不必要で黙っていることが時には最善の策であるということを表現します。この言葉は、場合によっては、対立や不和を避けるために口を閉じることが賢明であるということを示唆する場合もあります。
飼い犬に手を噛まれる
飼い犬は普段から飼い主に慣れ親しんでいる存在であり、予期せぬ手の噛みつきには驚きとともに悲しみや失望も感じるでしょう。同様に、信頼している人から裏切られることは、深い傷を負うことになります。この言葉は、信頼関係が重要であることを示唆する場合に使用されます。
三度目の正直
何かを達成するために何度も挑戦して失敗した後、最終的に成功することができるという意味です。この言葉は、挫折や失敗に直面した際に、再び立ち上がってチャレンジすることの重要性を表現するために使用されます。また、成功するためには継続的な努力や忍耐力が必要であることを表現する場合にも使用されます。
宝の持ち腐れ
ある人が才能や財産を持っているにもかかわらず、それを活かさずに無駄にしている様子。この言葉は、人生において与えられた才能やチャンスを活用しないことが悔いになることを示唆するために使用されます。また、自分が持っているものを活かすことが重要であることを示す場合にも使用されます。
火のないところに煙は立たない
火がない場所には煙が立たないように、何らかの事象があるときには、その背後には何かしらの真実があるということを表現します。この言葉は、噂話や陰謀説が現実に基づいていることがあることを示唆するために使用されます。また、何かが起こった原因を考える場合にも使われています。
求めよ、さらば与えられん
何かを手に入れるためには、それを求め、努力して行動する必要があるということを意味します。この言葉は、何かを手に入れたいと思っている人に、ただ望んでいるだけでは何も手に入らないということを示唆するために使用されます。また、自分の人生を変えたいと思っている場合にも、何かを求め、それを手に入れるために努力することが必要であることも表現されています。
油断大敵
この言葉は、何かを行う際には、常に用心深く注意を払うことが必要であることを表しています。また、危険な状況に置かれたときには、油断しているとさらなる危険を引き起こす可能性があることを示唆するためにも使用されます。
ローマは一日にして成らず
大きな目標を達成するには、それを達成するための時間と努力が必要であることを示しています。この言葉は、ある成果を得るためには、努力や継続的な取り組みが必要であり、時間をかけて努力することが大切であることを表現するために使われています。また、成功には必ずしも急いで取り組むことが大切ではなく、焦らずに計画的に進めることが必要であることも示唆されます。
ことわざ検索数3600件
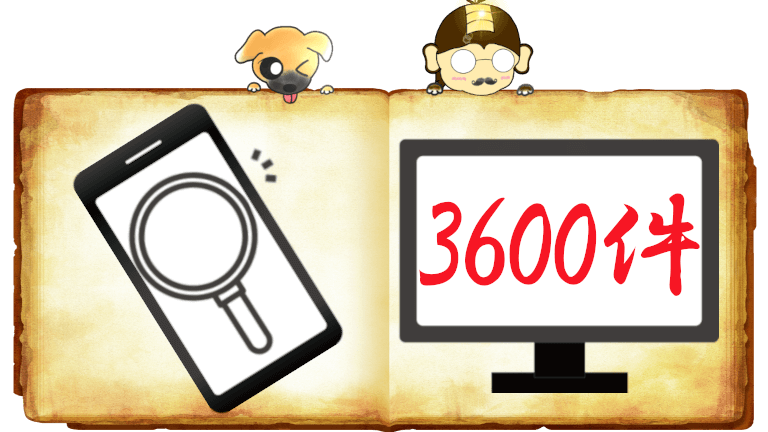
またまたまた減ってきた…月間約3600件ググられていることわざを見ていきましょう。
九死に一生を得る
九分通り助からない命をかろうじて助かる。
引用元: 広辞苑 第四版
九死~ほとんど死にそうなほど危うい場面~を乗り越え、何とか生き延びるという意味。
かろうじて逃げ延びる
・Have a narrow escape.
危なかったが逃げられた
・To cheat death.
死をごまかせた
自分とのバトル
通勤中、駅に向かう僕に徐々に迫ったきた欲望。
それは『お腹ピ~ゴロゴロ』という名の自分との闘い。『排出せよ!』という、時に空気読めよと思える自分からの強制命令。
しかし駅まであと10分。それまでトイレはない。。
走りたいけど(身体が揺れるから)走れない。何事もないように冷静さを保った振る舞いで可能な限り早歩き。
『駅のトイレに誰か入ってたら…ヤバすぎる。。』
あと数分、あと数メートル、あと1歩…そして!クールを装いトイレに向かって…やったぁぁぁ!
1つしかないトイレは誰も使用しておらず、九死に一生を得た僕は天国への入り口にゴールインした。
当たるも八卦当たらぬも八卦
中国語の慣用句で占いや予測は当たることもあれば当たらないこともあり、それを完全に信じることはできないということを意味します。この言葉は、人間には予測できないことが起こることもあるため、占いや予測を信じすぎず、自分で行動することが大切であることを示しています。また、占いや予測にすがることは自分自身の力を信じられないということも含まれています。
後は野となれ山となれ
「野となる」とは、野原に身を置くことで自由に行動できるということを意味し、「山となる」とは、山に身を置くことで見晴らしがよく、自然の力を感じることができるということを意味します。この言葉は、あらゆる可能性を尽くした結果、どのような状況に陥っても、その状況に合わせて最善の対処をする覚悟があることを示すために使用されます。また、「後は野となれ山となれ」という表現には、諦めや決断の強さ、精神的な強さが含まれているとも言われています。
一寸先は闇
この言葉は、人生や仕事、ビジネスなどの状況において、先の見えない不確定な状況が存在することを表し、あらゆる状況に対応するためには、柔軟性や適応力が必要であることを示唆します。また意外性や不確実性を前提とした注意深さや慎重さが必要であるという意味も含まれています。
親知らず子知らず
「親知らず」は、歯科医学用語で、智歯と呼ばれる奥歯の一種で、生えている場所が口の奥で見えにくく、抜くことが難しいことから、親にも子にも気づかれずに抜け落ちることがあるため、「親知らず」という名称がつけられました。この言葉は、秘密や隠し事が存在することがあり、お互いにそれを知らずに生きていることを表現しています。また、親や子が秘密や隠し事を抱えていることは、関係性を壊す原因となる場合があるため、親子関係を築く上で、オープンでコミュニケーションの取れる関係を構築することが大切であることを示唆しています。
腐っても鯛
「腐っても」は、腐った状態でも、それでもやはり、という意味を表し、「鯛」は高級な魚の一種で、その価値が高いことから「鯛」という言葉が使用されています。外見や状態が悪くても、本来の価値や素質があることを表現しており、人や物事を評価する場合にも使用されます。また「腐っても鯛」という表現には、価値を見抜く力や、物事の本質を見極める力が必要であることを示唆する意味も含まれています。
小人閑居して不善をなす
「小人」とは、心の狭い人や卑屈な人を指し、「閑居して不善をなす」とは、暇になって悪いことをするという意味です。この言葉は、何かに熱中することで、自分の精神を満たし、悪いことをしなくなることの重要性を示唆しています。また、大事なことに取り組むことで、小さなことにこだわらず、自分自身を高めることができるという意味も含まれています。
捨てる神あれば拾う神あり
「捨てる神あれば」とは、自分で何かを捨てることができる人がいるという意味で、「拾う神あり」とは、捨てたものを拾ってくれるような人がいるという意味です。この言葉は、何かを手放すときに別の良いことが起こる可能性があることを表現しています。また、この言葉は物質的なものだけでなく、人間関係や仕事など、様々な面においても適用されることがあります。
罪を憎んで人を憎まず
「罪を憎む」とは、悪事を厳しく非難することで「人を憎まず」とは、その人自身を憎んだりせず彼らに対して寛大であることを意味します。この言葉は人間関係や社会生活において、他者を尊重し彼らの過ちや悪事に対しても冷静な態度を取ることの重要性を示唆しています。また、この言葉は他人を許すことで自分自身が内面的にも成長し幸福を見つけることができるという意味も含まれています。
寄らば大樹の陰
「寄る」とは、助けを求めることで「大樹の陰」とは大きな木の下に庇われることができるように、大きな力を持つ人の保護や援助を受けることができることを意味します。この言葉は弱い立場にいる人が、より強い人の支援を得ることで安心して生活することができることの重要性を示唆しています。また、この言葉は相手に協力することで自分自身も成長することができるという意味も含まれています。
ことわざ検索数2900件
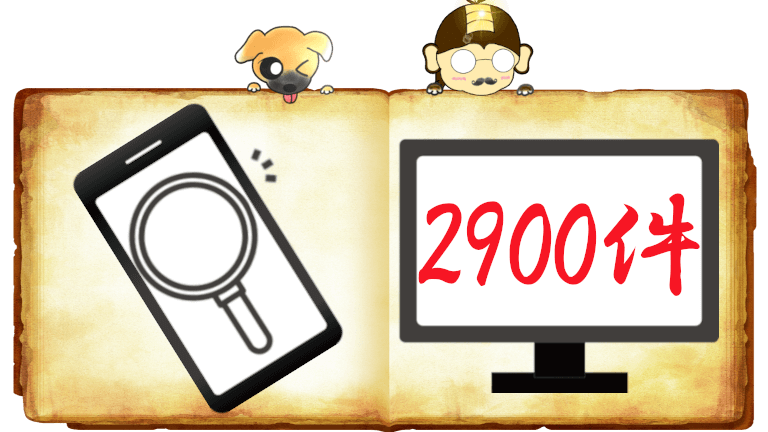
またまたまたまた減ってきた…月間約2900件ググられていることわざを見ていきましょう。
一難去ってまた一難
例えば、試験に受かったと喜んでいたら、次の課題や辛い仕事が待っていた、というように、問題が解決しても、新たな問題が現れることを表現しています。
この言葉は、人生においてもビジネスにおいても、何かを達成する過程で遭遇することが多く、常に自分自身を成長させるために前向きに考えることが大切です。
犬の遠吠え
犬が遠くで吠える様子を比喩的に表現した言葉。
例えば、誰もいない夜道を歩いているときに、自分の思いを大きな声で叫びたくなるように、犬が一匹で吠える様子に重ねて使われることがあります。
自分の感情や思いを抑え込むことが多く、自己表現や自己アピールが重要視される現代社会において自分の意見や考えを表明する勇気を与えてくれる言葉としても使われています。
鬼の居ぬ間に洗濯
他人に邪魔されずに勉強や仕事ができるときに、集中して取り組むことができるというような状況で使われます。
この言葉は古くから伝わる日本の民話に登場する鬼をモチーフにしており、鬼が居ないときに人々が仕事を進める話に由来しています。また鬼は邪気を祓う力を持っていると考えられていたことから、邪気を払って清々しい気持ちで物事に取り組むことができるという意味合いも含まれています。
仕事や勉強のみならず、日常生活の中でも静かな環境を利用して家事や趣味、リラックスする時間を作ることができるときに使われることがあります。
終わりよければすべてよし
何か問題や障害があっても最終的に良い結果が出れば、それまでの苦労や努力は報われるということを意味します。
この言葉は、良い結果が出るかどうか分からない状況~苦労や努力が報われるかどうか不安になってしまう人たちにとって、前向きな意味を持ちます。また人生において困難や苦労を乗り越えて最終的に幸せを掴むことができるという希望を与える表現としても使われます。
ただし、結果が全てであり過程については問題にしないという危険性もあるため、常に正しい手段や方法で物事を進めることが大切であるということも忘れてはいけません。
壁に耳あり障子に目あり
周りの人たちが自分たちの話を聞いたり、行動を観察している可能性があるということを警句しています。
社会において人々が互いに影響し合うことが多いときに、慎重に行動する必要があることを示唆しています。また、隠し事をしたり不正を行ったりするときには、いつでもその行動がばれる可能性があることも意味しているため、正直で誠実な行動を心がけることが望ましいとされます。
日本の古くからのことわざであり、家庭内での秘密や機密の扱い方を教えるために使われていたことがあります。また現代社会でも、人々が日常的に使う言葉として広く認知されています。
喧嘩両成敗
争いが起こった原因や経緯を十分に考慮し、双方に対して公正に判断する必要があることを表しています。
この言葉は、過去には身分や立場の強い者が弱い者を押さえつけていた場合に「両者にとって不利益な結果が生じる」ということを警告するために使われていたことがあります。現代でも、この言葉は論争や紛争を解決する上で中立的な立場から問題解決に向けたアプローチを行う必要があることを示唆しています。
ただし「喧嘩両成敗」は本来は正義を尽くすための言葉であり、暴力や過剰な力の行使を許容するものではありません。紛争を解決する際には、公正で正確な情報を集め、中立的な立場で問題解決を行うことが重要であることを忘れてはなりません。
虎穴に入らずんば虎子を得ず
成功するためには、リスクを冒し、チャレンジすることが必要だということを表しています。
この言葉の由来は、中国の春秋戦国時代に存在した諸侯国の一つである鄭国の話です。ある時、鄭国の軍師であった呉起は、敵の将軍である趙盾を捕縛するため、趙の陣営に単身で潜入し、趙盾を捕らえたという伝説があります。この話から、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という言葉が生まれました。
この言葉は、チャレンジ精神を育むためにしばしば用いられます。一方で、危険やリスクを過大に評価し冒すことが無意味である場合もあるため、常にリスクとリターンをバランスよく見極めることが重要です。
蛇の道は蛇
蛇は自分たちがよく知る環境で最も優れた行動を取ることができるため、他者が蛇と同じような環境で戦うことは非常に困難であるということを意味しています。
蛇が自分たちが生息する場所や狩り場を熟知し、自然の中で最も熟練した狩猟者であることに由来しています。つまり、蛇のように自分たちが得意とする環境で行動すれば成功する可能性が高くなるということを表しています。
自分たちの専門分野や得意分野であれば、自信を持って行動し他者をリードすることが可能という意も含まれます。
背に腹は代えられぬ
ある程度の犠牲を払っても、将来的な安全や安定を確保することが重要であるということを示唆しています。
この言葉は、日本の江戸時代に成立した諺で、背中に腹をかえるように、将来に備えて今の苦労や努力を惜しまずに取り組むことが大切であるということを表しています。つまり、将来に備えて、現在の努力が必要であるということを示唆しています。
ビジネスや投資など、将来的なリターンを追求する場合にも適用されます。リスクがある投資やビジネスを行う場合、ある程度のリスクを負わなければならない場合がありますが、将来的な安定や成功を目指すためには、そのリスクを取ることが必要であるということも示唆しています。
年貢の納め時
日本の江戸時代には、年貢の納付期限が厳格に定められており、期限を過ぎると罰則が科せられたため、納め時を逃すことは許されませんでした。そのため、「年貢の納め時」という言葉は、時期を逸すると大きな損失を被ることになる意も含まれています。
ビジネスやプロジェクトなどの場面でも用いられ、計画やタスクの進捗管理において、期限を守り、スケジュール通りに進めることの重要性を表しています。遅れてしまった場合、プロジェクトの成功を妨げる可能性があり、大きな損失を被ることになるため時期を逃すことは許されないということを示唆しています。また、締め切り前に作業を終わらせることができれば、余裕を持って次の作業に取り組むことができるため、仕事の質や効率を高めることができます。
残り物には福がある
あきらめずに、再利用やリサイクルを行うことで、新たな価値を生み出すことができるということです。
もともとは食物に関連した言葉で、食べ物を大切にし無駄にしないことが、幸せをもたらすということを表しています。また物事に対する視点や捉え方を変えることができれば、新たな発見やアイデアを生み出すことができるという意味も含まれています。
ビジネスや日常生活でも、この言葉は有効であり、残った資源や情報を活用することで新たなビジネスチャンスを見出すことができたり、コスト削減につながることがあります。また、既存の製品やサービスを改良して、新しい価値を生み出すこともできます。したがって、「残り物には福がある」ということわざは、賢くリサイクルし、効率的に資源を活用することが、ビジネスにとっても、社会にとっても重要であることを示しています。
貧乏暇なし
貧しい人たちは生活のために必死に働き、暇な時間がないということを意味しています。
この言葉は、日本の昔話「蟹工船」に登場する言葉で、貧しい漁師たちは、日夜漁に出て食べるための蟹を取って生活を維持していました。彼らには暇な時間がなかったため、子供たちも一緒に働かざるを得なかったとされています。
この言葉は、貧困層が持つ現実的な問題を示していると同時に、時間を有効に使うことの大切さを教えてくれます。時間は限られており、有効に使わなければ人生において後悔を残すことになります。貧乏暇なしという状況にある人たちは、暇な時間を作ることができないため、より一層時間を有効活用することが求められます。現代社会においても忙しい生活を送る多くの人たちにとって、時間の大切さを教えてくれる言葉となっています。
論より証拠
単に口で言葉を並べるだけではなく、実際に証拠を示すことで論を説得力のあるものにすることが必要であること。
主に法律や裁判所においてよく使われます。裁判では被告人が罪を犯したかどうかを証明するために、様々な証拠を提示する必要があります。口頭で主張するだけでは説得力に欠けることが多いため、具体的な証拠を示すことが求められます。
また、ビジネスの世界でもこの言葉がよく使われます。企業間のトラブルや契約の際には、約束したことを実現するために、具体的な証拠を提示することが必要となります。証拠があることで、約束や主張がより信頼性が高くなり、相手を説得することができるのです。
論より証拠は言葉だけでなく、具体的な証拠を示すことが説得力のある主張をするために重要であることを表し、法律やビジネスの分野だけでなく日常生活でも有用な考え方です。
ことわざ検索数2400件
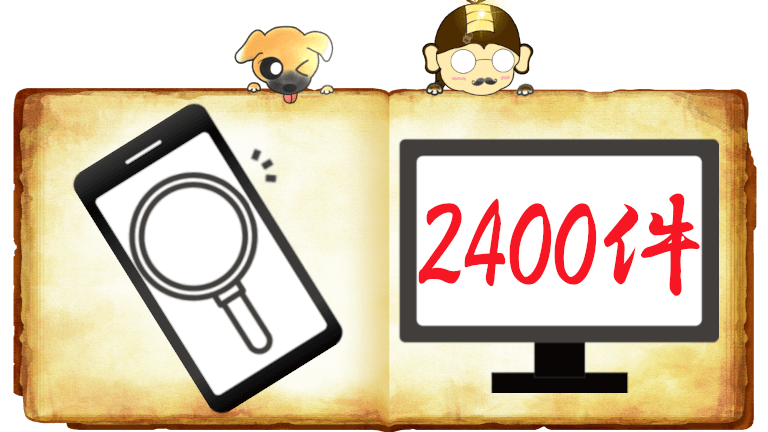
またまたまたまた減ってきた…月間約2400件ググられていることわざを見ていきましょう。
老いては子に従え
この言葉は、家族や社会において年長者が尊重される文化的な価値観を表しています。
年長者は経験や知識を持ち、そのために尊重されるべきだとされています。一方、若者たちはまだ経験が浅く、知識も不足しているため年長者の指導や助言に従うことが重要だとされています。
家族内や職場など、あらゆる場面で用いられることがあります。ただし近年では、若者たちが自己表現や自立心を重視する傾向があるため、この言葉が完全に当てはまるかどうかについては、議論があるようです。
死人に口なし
このことわざは、死者を尊重する文化的な価値観を表しています。死者は、生前に言っていたことやしていたことが後世に語り継がれることがありますが、それは遺族や友人または書物などの記録を通して行われるものであって直接的な証言はできません。
また、秘密を守ることの重要性をも示唆しています。人々は生前に秘密を共有していた人が亡くなった後その秘密を守ることが求められることがあります。
日本だけでなく世界中でよく使われるものであり、死者を尊重する態度や秘密を守ることの重要性を教えてくれます。
敵は本能寺にあり
このことわざの由来は、織田信長が本能寺において明智光秀に襲撃された事件(本能寺の変)にあります。織田信長は、光秀を信頼しており反逆を起こすことを予想していませんでした。しかし光秀は裏切り信長を襲撃したため、このような言葉が生まれたとされています。
敵を探すのに遠くに行く必要はなく、身近なところにいる可能性があることを表しています。そのため、常に周囲に注意を払い、油断せずに用心することが大切だという教えが込められています。
戦国時代に生まれた言葉であり、現代においてもその価値は変わらず、私たちは常に周りに気を配り危険を察知し予防策を考えることが求められるといえます。
百聞は一見に如かず
物事を理解する上で視覚的な情報が重要であることを示しています。たとえば、食べ物の味や色、景色の美しさなどは、見た目から得られる情報が大きいため、何度も聞いたところでそれほど理解が深まらないことがあります。
また、このことわざは理論だけでなく実践が大切であることをも示唆しています。たとえば、スポーツや芸術などは、理論を学んだだけでは上達しないことがありますが、実際にやってみることで自分自身で体験し学ぶことができます。
日本だけでなく世界中で広く使われているものであり、多くの人が共感する価値観を表しています。何度も話を聞くよりも一度現場を見たり、体験したりすることで、より深く理解することができるということです。
負けるが勝ち
長期的な視点で物事を捉え、短期的な敗北を乗り越えて大きな成功を収めることができることを示しています。失敗を繰り返したことがきっかけで新たなアイデアを思いついたり、それまで気づかなかった課題に気づいたりすることがあります。そのような経験を通して、より成長し成功への道を切り開くことができるのです。
また、勝利や成功にこだわりすぎることが逆に自分を苦しめることがあることも示唆しています。目的を達成するために、倫理的な問題を無視したり他者を傷つけたりすることがあるかもしれません。しかし、それでは長期的には自分自身を苦しめることになるため、目的を達成することができたとしても本当の意味での勝利とは言えないのです。
成功を追求する上での姿勢や哲学を示し、長期的な視点で物事を捉えることの重要性を教えてくれます。
歴史は繰り返す
人間社会の歴史が一定の法則性やパターンに従って進んでいることを示しています。経済的な危機や社会的な問題などは歴史的に何度も繰り返されてきました。そのため、歴史を学び同じ過ちを繰り返さないことが大切であるとされています。
また、人間の行動や判断には誤りがつきものであることを示しています。歴史の中には正しいと思われた行動や決定が後に大きな失敗を招いた例があります。そのため、歴史的な出来事を研究し過去の失敗や成功の要因を分析することで、より良い判断を下すことができるようになるのです。
このことわざは、日常生活においても応用することができます。過去に同じような問題や失敗を経験した場合には、歴史を繰り返さないように、適切な判断を下すことが大切です。
全ての道はローマに通ず
古代ローマ帝国が支配していた時代、ローマが巨大な帝国であったため多くの道や交通路がローマに向かって整備されていたことが由来とされています。つまり、どの方向から来ても最終的にはローマに行き着くことができるという意味です。
このことわざは、多様な方法や手段があるものの、最終的な目的や目標は同じであることを表しています。たとえば、ある目標を達成するためには異なるアプローチや手段がありますが、最終的には同じ方向に向かっているため、目標達成に向けての取り組みにつながるということです。
また人生においても応用することができます。人生には様々な選択肢や道がありますが、最終的には幸せや成功に向かっていると信じ選択や行動を進めることが大切であるということです。どのような選択をするにせよ、最終的に自分自身が望む方向に向かっているかを見据えることが重要です。
ことわざ検索数1900件
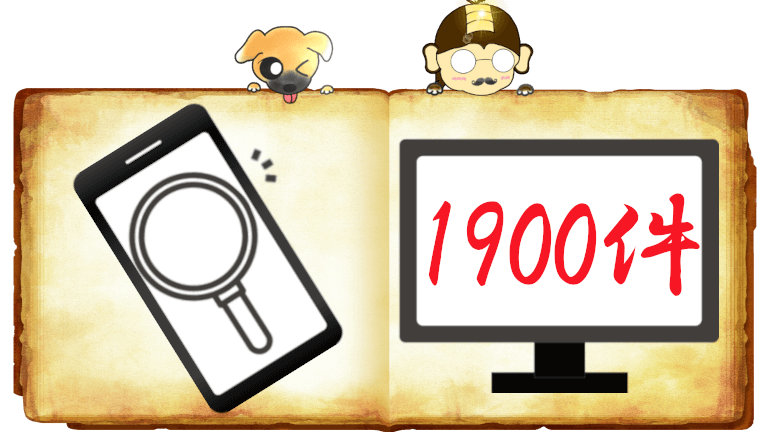
うん知ってる!月間約1900件ググられていることわざを見ていきましょう。
嵐の前の静けさ
天気現象の嵐に限らず、ビジネス、政治、社会などの様々な分野で使われます。例えば、会議や交渉の前には一時的に意見がまとまったり、緊張感が緩んだりする場合があるため「嵐の前の静けさ」と表現されることがあります。
思い立ったら吉日
これは、ためらわずに行動に移すことが大切であるという意味があります。このことわざは、仕事や学習、趣味など、あらゆる場面で有効なアドバイスとなります。
※この英語verは『善は急げ』でも同等の表現として扱われています。
攻撃は最大の防御
「攻撃は最大の防御」は、一部の人々が信じている言葉ですが、危険とも言われている信念でもあります。
攻撃的な行動が相手の反発を招き、より悪化する可能性があります。正しい戦略は、攻撃的な行動ではなく、防御的な行動を取ることだとの意見もあるのです。防御は、攻撃に対する対処方法を用意し、攻撃を受けたときに自分自身や他人を守ることができます。
逃した魚は大きい
釣りをする人が、釣り上げた魚を逃してしまったときに、その魚が自分の手から逃げてしまったことを後悔する気持ちを表現したものです。チャンスを逃したときに後悔する気持ちを表しており、機会を逃すとそれが本当に価値があったと気づくことがあるという意味があります。
地獄の沙汰も金次第
このことわざは、お金があれば、問題を解決することができる場合があることを表しています。しかし、お金が全てではなく富や財産だけで人生を豊かにすることはできません。そのため、お金を得ることは大切ですがその価値や使い方についても考える必要があります。
事実は小説よりも奇なり
こ実際の人生や出来事には、想像を絶する出来事が起こる可能性があることを表しています。小説やフィクションは、作者が創作したものであり、人生には起こりえないような設定や展開が含まれていることがあります。しかし、実際の出来事は、創造力を超えた奇妙で驚くべきものがあることを表現しています。
逃げるが勝ち
このことわざは、時には戦うことよりも逃げることが、より良い結果をもたらすことがあることを示しています。例えば、危険な場所や事故現場から逃げることが、自分自身や他の人々の命を救うことにつながる場合があります。また、人間関係においても、時には言い争いや口論を避け、適切なタイミングで話し合うことが、より良い結果をもたらすことがあります。逃げることが必ずしも悪いことではなく、状況によっては最善の策である場合もあるということを表しています。
濡れ手で粟
この言葉の意味は、手が濡れているために粟が手に付き、簡単に取ることができるということから来ています。例えば、何かをするのに特別な努力をせず、比較的簡単に成功を収めることができる場合、この言葉が使われることがあります。また、運が良いことや、相手が甘いということも、この言葉が使われる理由の一つとなります。ただし、このように容易に成功を収める場合でも、運に頼ることなく、自分自身の力で成し遂げることができるようになることが望ましいとされます。
乗りかかった船
船出をし、すでに大きな海原の中におり容易に引き返すことができない状況なら、引き続き航海を続けていこうというたとえ話に由来している言葉です。
物事を進め、すぐに辞めることができない状況にあるなら、打開策も考慮しながら続けていってみようという意味も含んでいます。
腹が減っては戦ができぬ
身体の健康状態が仕事や活動に大きな影響を与えることを表しています。例えば、仕事や勉強をする前に十分な食事を摂ることが重要であることや、スポーツや運動をする際にも十分な栄養と水分を補給することが必要であることが示されています。空腹であっても我慢をして仕事や活動を続けることができるわけではなく、身体に十分なエネルギーを与えることが大切であることを表しています。
忙中閑あり
多忙な状況でも適切な時間配分や優先順位の設定を行うことで、余暇を作り出すことができるということを表しています。また、多忙な人は、時間管理能力が高く効率的に仕事を進めることができるという意味も含まれています。時間を有効活用するためには自分自身の状況を正しく把握し、計画的に行動することが重要であることが示唆されます。
目糞鼻糞を笑う
自分自身の問題を見つめ、改善することが重要であることを示しています。また、他人を批判する前に自分自身に問題がないかをよく考えるように促すことも意味しています。このことわざからは自己批判的であることが大切であり、他人を批判する前に自分自身を見つめ直すことが必要であるという教訓が得られます。
ことわざ検索数1600件
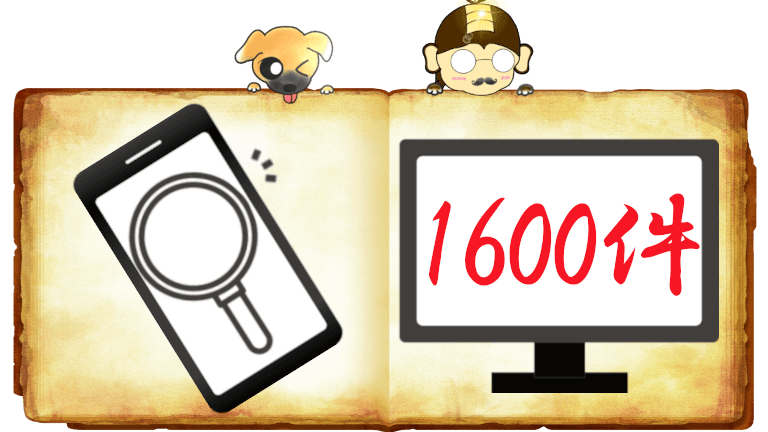
うんうん知ってる!月間約1600件ググられていることわざを見ていきましょう。
頭隠して尻隠さず
窮すれば通ず
人間は危機的な状況に置かれると、本来持っていない力やアイデアを生み出すことができるということを表しています。例えば、お金に困っているときには、探したことのない様々なアルバイトや副業を見つけ出す可能性を高める事ができます。このことわざからは、苦しい状況に陥ったときに柔軟な発想と努力で切り抜けることができるという希望が感じられます。
英語では “Necessity is the mother of invention” と表現されます。
正直者が馬鹿を見る
時として正直であることが、他の人よりも不利な状況を作り出すことがあるということを示しています。たとえば、詐欺師や悪徳商人との取引では、正直であることが裏目に出て損をすることがあります。また、正直に物事を言ったり行動したりすることが、時には人間関係を悪化させることもあるでしょう。
しかしながら、正直であることは社会的信頼を築くためには非常に重要であり長期的にはメリットを生むことがあります。正直な人は信頼できる人物として周囲から尊敬され、良い人間関係を築くことができます。また、仕事やビジネスにおいても正直であることは信頼性を高め、長期的な成功につながることがあります。
したがって、このことわざは正直さと利益の間には時に矛盾が生じることがあるということを示していますが、正直さを貫くことが信頼や成功につながるということを忘れずに、行動することが大切です。
初心忘るべからず
人が何か新しいことを始めた時には、初めのうちは熱意や意欲が高まり、情熱的に取り組むことができます。しかし、時間が経つと、慣れや飽きが生じモチベーションが下がってしまうことがあります。そのような時に、「初心忘るべからず」という言葉が、再び初心を思い出し熱意を取り戻すきっかけとなることがあります。
何かを始める際には、目標や目的を明確にし、そのためには何をすべきかを考え熱意を持って取り組むことが大切だとも教えています。また取り組みが進んでいく中で初めの熱意を忘れず常に初心に帰り、自分自身を振り返り改善していくことが必要であるということも示唆しています。
このことわざは、特に長期的な目標に向かって努力する場合に途中で挫折しないようにするためにも重要なメッセージを伝えています。初めの気持ちを忘れずに、コツコツと努力を続けることが、最終的な目標達成につながることを忘れずに行動することが大切です。
急いては事を仕損じる
時間が限られている場合や締め切りが迫っている場合でも、焦らずに冷静に考え計画的に行動することが重要であることを表現しています。急いで仕事をしたり決定を下したりすることで、思わぬミスやミステイクを犯すことがあるためです。
また、仕事やプロジェクトなどの計画的な進め方にも応用されます。計画を立てる際には余裕を持ったスケジュールを設定し、適切な期限を設けることが大切です。計画通りに進まない場合でも急いで判断や決断をするのではなく、冷静に対処し適切なアクションを取ることが重要です。
このことわざは、仕事やプロジェクトに限らず人生においても応用されます。人生の決断や選択をする際にも、短期的な利益にとらわれず、冷静に考え慎重に行動することが必要です。時間をかけて準備をし計画的に行動することで成功につながることが多くあると言われています。
船頭多くして船山に上る
仕事やプロジェクト、または社会的な問題を解決する際にも応用されています。困難な課題やプロジェクトに取り組む場合、単独での取り組みでは限界があります。しかし、多くの人が協力し知恵を出し合うことで問題を解決することができる可能性を広げるのです。
この言葉はリーダーシップについても示唆しています。リーダーが多くの人々を引っ張り、統率し目的に向かって進むことが大切であることを示しています。リーダーが多数のメンバーを率い、全員が協力して目的に向かって進むことができれば、成功の可能性は高くなります。
また、チームワークについても示唆しています。多くの人々が協力し仕事を分担することで、より効率的に仕事を進めることができます。個人の力に頼らず協力して進むことで、成功につながることがあります。
血で血を洗う
報復のために、同じように傷害を加えることを示しています。
暴力や復讐による問題解決を批判するために用いられることもあります。報復は通常、悪い状況を悪化させサイクルを繰り返すことがあります。また復讐行為は、しばしば法的、倫理的、または道徳的な問題を引き起こし、さらなる混乱や犠牲をもたらすことがあります。
一方で、このことわざが用いられる状況としては、己防衛のための適切な措置を取る必要がある場合が挙げられます。また、社会的に認められた刑事法や民事法の範囲内で法的手段を用いて正当な報復を行うことは、犯罪の軽減や正義の回復に寄与することがあります。
復讐による問題解決を避け、対話や妥協などの穏健な手段を模索することの重要性を示唆しています。戦いや紛争を解決するためには、相手との協力、助け合い、許し合いが必要であることを教訓として伝えている言葉でもあります。
二度あることは三度ある
過去に同じようなことが起こった場合、再び同じような状況が発生する可能性が高いという意味合いがあります。
経験を重ねることで失敗を回避したり、同じ間違いを繰り返さないようにするための警句として用いられることがあります。また、同じ過ちを繰り返す人を戒めるためにも使われます。
ただし、このことわざを過信してしまうと、過去の経験にとらわれすぎて新しいアイデアや新しいチャレンジを恐れることにつながることがあるため注意が必要です。過去の失敗や成功を振り返りつつも、常に新しいことに挑戦する姿勢を持ち続けることが大切です。
必要は発明の母
必要性や困難がある状況に直面することが、新しいアイデアや技術の発明を促す原動力となるということです。
人々が課題に直面した場合に、問題を解決するために自分たちで工夫を凝らすことの重要性を示しています。また、特定の目的やニーズに応じたアイデアや技術の発明は、社会や経済に重要な貢献をすることができます。
例えば、現代社会においては気候変動やエネルギー問題など多くの課題が存在しています。これらの問題を解決するために、新しい技術や革新的なアイデアが必要であり、このことわざが示すように、必要性があるからこそ、新しいものを生み出すことができると言えます。
創造的な思考を促し、問題を解決するためには問題そのものを認識し、その問題に対するニーズに基づいて対応することが重要であることを表現しているのです。
坊主丸儲け
「少ない投資で大きな利益を得る」という意味合いがあります。
この言葉は、江戸時代に仏壇を販売する際、仏像の丸い頭部を指して「坊主丸」と呼んだことに由来します。仏壇の売り手たちは、坊主丸を作ることで投資額よりも大きな利益を得ることができたとされています。このように、小さな投資で大きな利益を得ることができる例が坊主丸儲けの語源となったと言われています。
現代においても、この言葉は少ないリスクで大きな利益を得ることができるビジネスチャンスを表現するために用いられることがあります。しかし、その反面リスクを回避しすぎるあまりにチャンスを逃してしまうこともあるためビジネスにおいてはリスク管理が重要であると言えます。
眉に唾をつける
つまり相手が言ったことが本当かどうか疑い、その真偽を確かめる必要があるということです。
この表現の由来には諸説ありますが、一説によれば、昔、手形などの書類に印鑑の代わりに唾をつけて証明していた時代があり、その唾が眉にかかっていたことから、信用できるかどうか疑っていたという説があります。また、あるいは「眉に唾をつける」のような言葉が使われるようになったのは、江戸時代の噺家たちが、聴衆に対して自分たちが語る話を真実だと信じてもらうために、自分たちの眉に唾をつけることで自分たちが嘘をついていないことを示したことからきているという説もあります。
現代では、この表現は相手の話を疑っていることを示すために用いられます。ただし、あまりにも疑いすぎると相手との信頼関係が損なわれることもあるため、適度な疑いと信頼のバランスが大切であると言えます。
藪をつついて蛇を出す
例えば、ある問題に対して必要以上に手を出してしまって結果的に新たな問題を引き起こすということが挙げられます。
この言葉の由来については、藪の中には蛇が潜んでいることが多く藪をつついて蛇を出してしまうことがあるため、手を出す必要のないことに無闇に手を出すことが問題を引き起こすことになる、という教訓が込められています。
冷静な判断力や事前の情報収集などが必要であることを示すために使われます。あまりにも軽率に行動してしまうと余計な問題を招くことになります。したがって事前に情報収集を行い冷静な判断をすることが重要であると言えます。
ことわざ検索数1300件
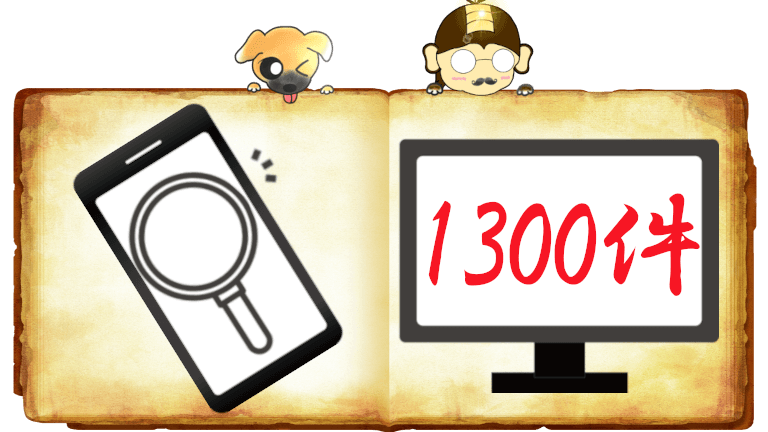
うん知ってる?月間約1300件ググられていることわざを見ていきましょう。
芸は身を助ける
この言葉の由来には、江戸時代の庶民の間で、芸事を習得することが社会的地位の向上に繋がると考えられていたことが関わっています。当時、芸事に秀でた人は、その技術を生かして、商売をしたり、社交界で成功したりすることができました。
現代でも特定の技術や才能を持つことで、それを生かして自分自身を助けることができると言えます。例えばプログラミングやデザインなどの専門技術を身につけることで将来に向けて自分自身を守り、生計を立てることができます。また趣味として音楽やスポーツを習得することで自分自身をリフレッシュし、ストレスを解消することができます。
人生の中で何か特定のことに熱中することが大切であることを示すために使われます。一つの分野に秀でることで人生がより豊かになる可能性があります。
泣き面に蜂
この言葉の由来には、蜂が刺すことで痛みを引き起こすことと、泣いている人が悲しみを感じている時に追い討ちをかけるような言動が行われることが同様に痛みを引き起こすということが込められています。
例えば、友人が失恋して泣いているところに「あなたは彼を信じていたから、自業自得だよね」と言ってしまうようなことが「泣き面に蜂」の例です。本来なら励ましてあげるべき相手に対して、逆に追い打ちをかけてしまうことで相手に傷をつけてしまいます。
相手の気持ちに寄り添、同情することが大切であることを示すために使われます。相手が悲しんでいるときには、その気持ちに寄り添い心の支えとなってあげることが大切です。
汝自身を知れ
自分自身をよく知ることで、自分の長所や短所、能力や限界を把握し自己改善や成長のための方向性を見出すことができます。
この言葉は、古代ギリシャの哲学者ソクラテスが口にしたとされています。ソクラテスは知恵こそが人間にとっての至高の徳であり、そのためには自己を知ることが不可欠であると考えていました。
自分自身を客観的に見ることができるようになると、自分の思考や行動に対する反省ができるようになります。自己分析を行うことで自分自身が何に向いているのか、何を目指すべきなのかを明確にすることができます。
また自分自身をよく知ることで、他人とのコミュニケーションが円滑になります。自分自身がどういう人間であるかを把握することで他人に対する理解や配慮ができるようになります。
ことわざ検索数1000件
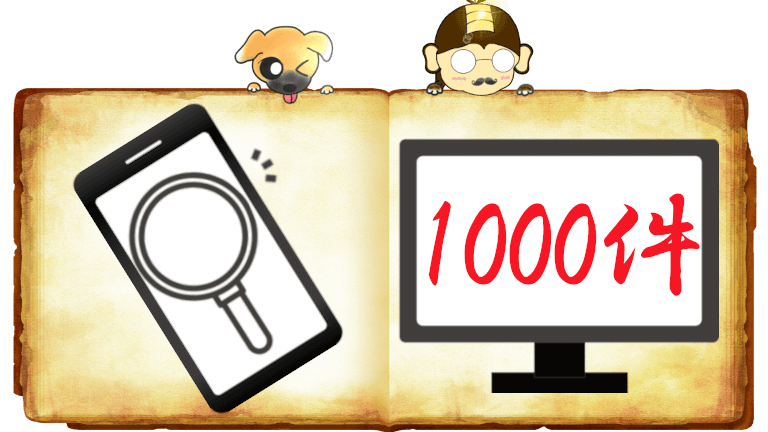
知ってる?月間約1000件ググられていることわざを見ていきましょう。
この親にしてこの子あり
子どもが育つ環境や家庭環境は、その後の人生に大きな影響を与えるとされています。
この言葉は古代中国の儒教思想から来ています。儒教では、家族や親族、社会の構成員の関係が非常に重要であり家族の中での個人的な責任や道徳的な義務が強調されています。
親が子どもに与える影響は大きく、親の行動や価値観、教育方針が子どもの性格や思考に反映されることがあります。親が子どもに対して愛情を持って接し正しい方向に導くことで子どもは良い方向に成長することができます。
一方で、親の欠点や誤った教育方針が子どもに影響を与え問題を引き起こすこともあります。子どもは親が示す態度や行動をよく観察し、それを模倣することがあるため親自身が正しい生き方を見せることが大切です。
親の心子知らず
親と子どもの間に存在する感情的な隔たりや理解不足を指します。
子どもは成長するにつれて独自の考えや価値観を持ち、親とは異なる方向に進みたいと思うことがあります。また、子どもが直面する問題や悩みは親が想像するよりも複雑であったり子ども自身が語りづらいものであることがあります。
一方で、親は子どもに対して強い愛情を持ち良い方向へ導きたいと思っているため、自分の思い通りに動いて欲しいと願うことがあります。しかし子どもにとっては、そのような親の思いは分からず自分自身の方向性や自由を求めることがあります。
この言葉は、親子間のコミュニケーションが不十分であることが問題を引き起こすことを警句しています。親は子どもの考えや気持ちを理解し共感することで、より深い絆を築くことができます。また、子どもに対してオープンであり続けることで子どもが悩みや問題を共有しやすくなり適切なサポートを受けることができます。
学問に王道なし
つまり、学問は自由度が高く自分自身で考えることが重要であり自分なりのアプローチを追求することができるということです。
学問において、既存の学説や理論を疑問視し新しいアプローチを模索することが求められる場合があります。そのような場合には、常識や決まりごとにとらわれず自分自身で物事を考えアイデアを生み出すことが重要となります。
また学問には目的があり、その目的に向かって取り組むことが大切です。しかし、その目的達成のためには必ずしも王道や正解が存在するわけではなく自分自身で考え、試行錯誤することが求められます。
「学問に王道なし」は、学問において自由度や柔軟性が求められることを示しています。正しいやり方や決まったルールがあるわけではないため、自分自身で考えアプローチを追求することが大切であるということです。
最後に
元々特別なことわざに、あえてNo1検索数をご紹介しました。
情けは人の為ならず!人の事を思いやる意味を持つ素晴らしきことわざがNo1。
ただそれ以外にも人生の教訓となる言葉はたくさんありました。
みなさんは今後、どんなことわざを使いたくなりましたか?
過去の人々の教訓を活かしながら、これからの未来を生きていけたらイイですね🙂